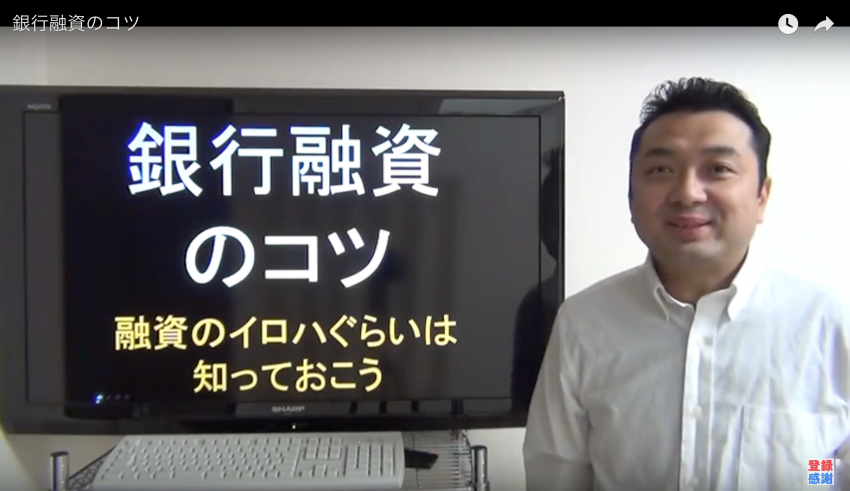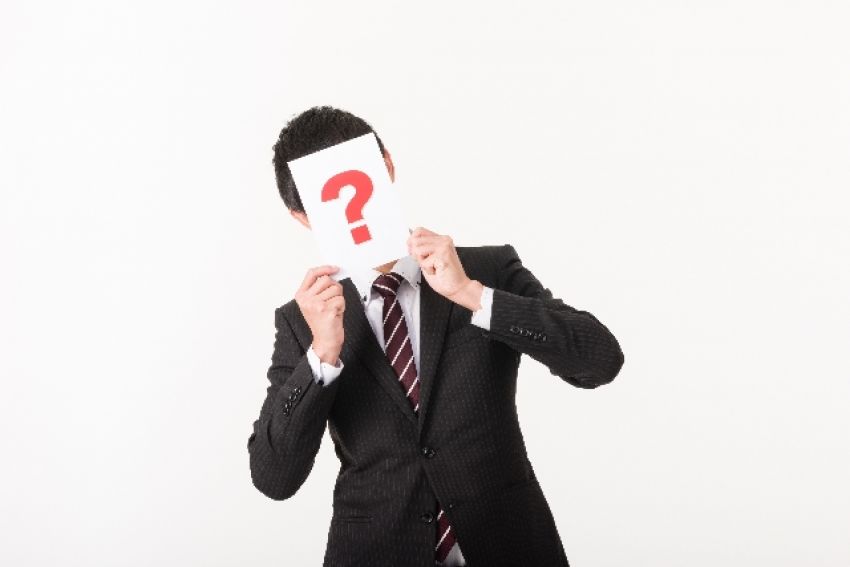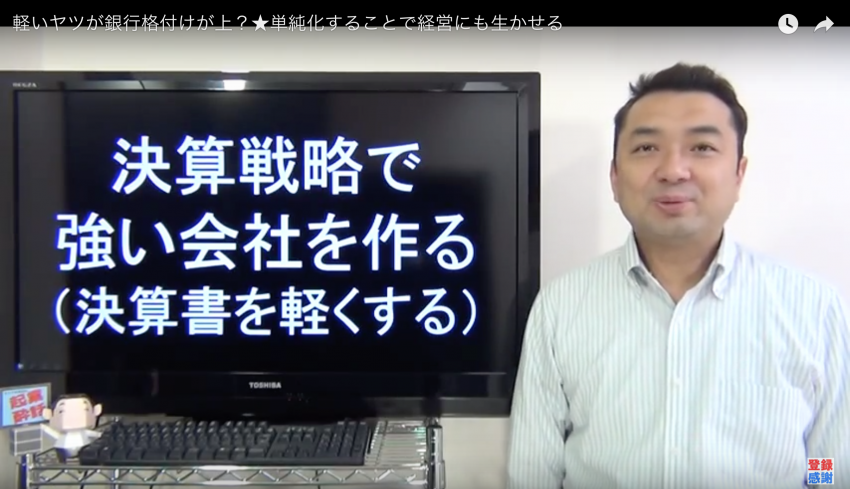財務– category –
-

福岡市内のスタートアップ企業は融資保証料が脅威のゼロに!
平成28年より福岡市内でスタートアップ企業が融資を受ける際は、保証料がゼロとなる制度が発足しました。これから創業をお考えであれば「保証料とは何か?」という疑問に当たることもあるでしょうから、福岡市の優れた制度と共に簡単に、保証料について説明していきたいと思います。 -

キミアキ先生直伝!銀行融資のイロハと融資をうまく受けるコツ
中小企業が存続するために、経営の命綱となるのが資金調達、つまるところ銀行融資です。ところが多くの経営者が「銀行融資をうまく受けるコツと融資のイロハ」を、あまり知らないのが実状です。そこで本日は、資金調達のプロフェッショナル・キミアキ先生に融資のあれこれを教えていただきます。 -

マイナンバーの浸透で副業する人を雇う側まで大損!なぜ?!
マイナンバー制度がスタートしたことにより、副業やダブルワークが「会社にバレルのではないか?」と戦々恐々になっているサラリーマンやOLが増えています。一方で、副業やダブルワークする人を雇う側にも注意が必要になります。源泉所得税の徴収で、処理をきちんと行わなければ大損する可能性があるからです。失敗例と共に対策方法を徹底解説します。 -

就業規則の雛形利用で節約のはずがウン百万の損…一体なぜ?
インターネットや書店等では、簡単に就業規則の雛型を入手することができます。特にお金を節約したい創業時に、多くの方がモデル就業規則を使って自社の就業規則を作ります。ところが安易にモデル就業規則を使うと、思わぬ落とし穴にハマります。モデル就業規則の安易な使用によるリスクをどのように軽減できるか考えてみましょう。 -

振替休日と代休はどちらが会社にとって節約につながるの?
「振替休日」と「代休」の違いを、読者の皆様はご存知ですか?両者は法律的に明確な違いを持っており、給与の支払額もどちらを利用するかで全く変わってくる制度です。会社が計画的に休日出勤の人件費を節約するとしたら、振替休日と代休のどちらを社員にとってもらうのがオトクか解説いたします。 -

退職金は数十年後どうなる?雇われる側が今から立てるべき対策
退職金を払う・払わないに関しては、原則として会社(雇用者)の自由となっている。ただし、終身雇用制度が崩れ、転職が当たり前となった現代社会においては、雇用する側にも、雇用される側にも、現行の退職金制度が陳腐化しくことは目に見えている。20年後に向けて、今雇われる側が起こすべき行動とは何なのだろうか? -

これを読めば解決!「補助金」と「助成金」って何が違うの?
「補助金」と「助成金」名前は似ているけれど、制度のどこがどう違うのか?答えられる人は意外と少ないようです。そこでお金のプロが、補助金と助成金の共通点と相違点を解説してくれます。更に両者のうち、代表的な制度も3つずつあげていただいた上で、利用するメリットと注意点を指摘していただきます。これを読めば、補助金も助成金もまるわかりです。 -

実は良い面だけではない!フレックスタイムの抱えるデメリット
ダイバーシティ(多様な人材を活用すること)の推進や、労働時間の短縮、人件費の削減及び生産性の向上を目指して、フレックスタイムを導入する企業が増えています。フレックスタイムにはもちろん良い面もありますが、導入を検討するなら、デメリットも踏まえておく必要があるでしょう。フレックスタイムのデメリットを2つ提示します。 -

中小零細企業から体力を奪う社会保険という日本の悪制度
「正社員を雇うと潰れる」パッと聞いた方で、実感のある方は、もしかすると中小零細企業の経営者かもしれません。それくらい、中小零細企業にとって人を雇用することは、リスクと隣りあわせなのが現実です。この問題を増長しているのは、ズバリ社会保険制度だと、キミアキ先生は斬りこみます。社会保険制度の矛盾とは?解説していただきます。 -

重大な問題を抱えた社員を雇わぬため会社で事前に出来ること
優秀な人材を雇うことは、採用において大きな課題ですが、能力はもちろんのこと労務管理の観点から、従業員採用を考える必要もあります。なぜなら雇用した社員が重大な問題を起こす人間である場合、会社は大きな損害を被らざるを得なくなるからです。どうやって、この問題を回避できるか?労務のプロが解説してくださいます。 -

社長が退職金を貰えて個人事業主が貰えないのはなぜなのか?
退職金制度は会社が任意で設定できるものであり、絶対に設定されなければならないものではありません。ところで法人企業では、社長も退職金をもらうことが可能ですが、個人事業主は退職金をもらうことは可能なのでしょうか?答えはNOです。なぜ個人事業主は退職金をもらえないのか?代替措置となる制度はないのか?解説いたします。 -

中小企業にもD&O(Directors & Officers)保険の間口が広がる
D&O保険とは、会社役員としての業務の遂行を原因として、保険の契約期間中に他社から損害賠償請求されたことで生じる損害を、保険期間中の総支払限度額いっぱい支払ってもらえる保険です。これまでは給与課税の対象でしたが、今年新たな保険料の税制改正が行われたことで、未上場会社にも加入しやすくなりました。株主訴訟のリスク回避などのため加入するのも一考です。 -

法人成り後の社会保険加入は本当にデメリットだらけなの?
個人事業主から法人事業者へ転換すること、いわゆる「法人成り」を実行する際に、気にかけることの1つとして「社会保険の負担が増えること」があります。国民健康保険+国民年金というケースから社会保険+厚生年金では、本当に負担が大きく増えるのでしょうか?社会保険に入ることは、本当にデメリットだらけなのか?税務のプロが例を用いて説明してくださいます。 -

業績の悪い時ほど熱い想いと明確な意思を社内報に吹き込め
社内報担当者は「社内報を通じて何がしたいのか」という想いと、明確な意思を持った人間でなければなりません。なぜなら、この想いと意思があるか否かは、企業の業績が厳しい時ほど、社内報の存在価値を高めるために役立つからです。「業績が悪いからつまらない社内報しか作れない」というのは言語道断。社内報から社内の閉塞感を吹き飛ばしましょう。 -

マイナス金利で影響を受ける生命保険を春のうちにチェックせよ
マイナス金利が導入されましたが、普段の生活に大きな影響を及ぼしていると感じている人は、まだ少ないかもしれません。しかし、「貸す」「預ける」「殖やす」という行為に対しては、今は完全なアゲンスト状態となっています。この影響を受けているのが生命保険会社で、保険商品の組み立てにもその兆候が現れ始めました。自分の生命保険を今一度チェックする方法を、資産運用のプロに解説していただきます。 -

法人保険に加入することでもたらされる2つの効果とは
会社の節税対策でお悩みの場合、法人保険を活用してみるのが1つの手かもしれません。法人の生命保険に入っておくと、利益を保険料として払い込むことができ、法人税を始めとする税金の納税額を実質的に減らすことが可能です。社員も加入対象となった場合は、福利厚生の効果も生じます。ただし加入時には、損金に出来る範囲とキャッシュフローに気をつける必要があります。 -

3次会接待の経費算入は無理ゲー?交際費にまつわる噂を斬る!
接待費用には、様々な噂があります。「3次会は交際費で落とせない」「アルコールが入ると会議費で落とせない」「キャバクラや風俗店へ行った費用は交際費で落とせない」などの噂です。実際のところはどうなのでしょうか?まずは交際費の正確な知識を得た上で、これら接待費用にまつわる噂に斬りこんでいきます。 -

日本の会社はなぜ3月決算を選ぶの?その理由を徹底解説!
日本企業の実に20%が決算月を3月に据えています。なぜでしょうか?大企業、特定の取引先を持つ企業、中小企業・個人商店毎に、その理由は全く異なるものとなります。更に、なんとなく3月を決算月として選んでいたなら、決算月を変えることでメリットが生じる場合もあるようです。走る税理士・鈴木さんが面白おかしく、深い内容で解説してくださいます。 -

来年の確定申告でドバっと活用したい新たな3つの控除項目
来年の確定申告に向けて、節税対策で活用可能な新たな控除が、平成28年度税制改正で決まりました。いずれの控除も、平成28年から3〜5年の間に期間を限定されたものばかりです。特に住宅関連の控除は、マイナス金利の導入による住宅ローン金利の低下と共に有効活用できそうです。オトクに活用したい新たな控除を3つご紹介したいと思います。 -

銀行格付けもUP!軽い決算書を作るための具体的な5ステップ
中小企業にとって、簡素化された決算書を作成することは、会社の経営判断を迅速に行う上でも、銀行からの評価をあげる上でも、非常に重要なことです。しかし殆どの企業はそれが出来ていません。キミアキ先生が、決算書を軽く(簡素化)するメリットを、銀行格付けを上げる強い決算書の具体的な作り方と共に解説してくれます。