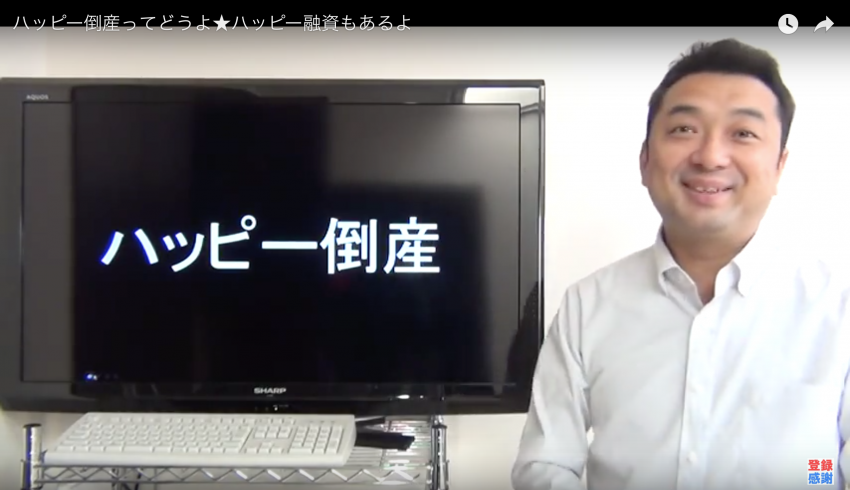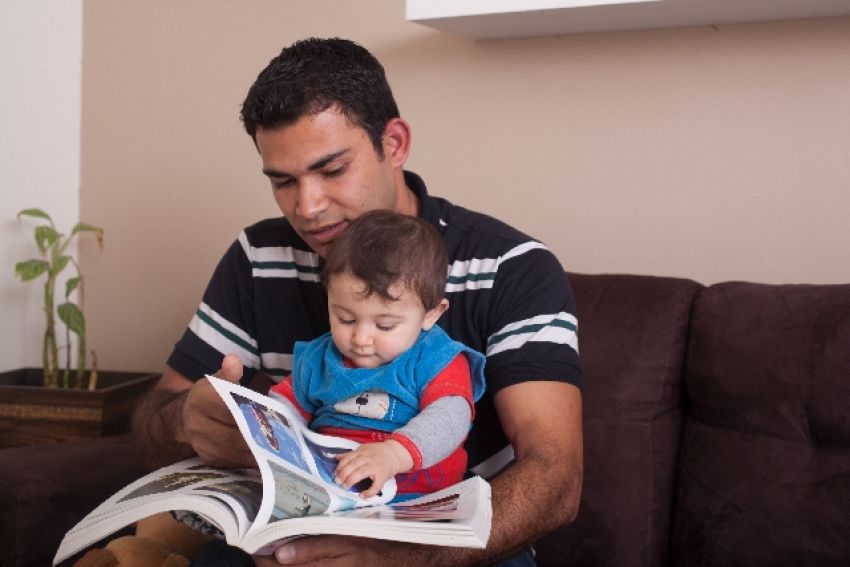財務– category –
-

誤解の多い助成金:経営者が答えに詰まる8つの疑問に回答
助成金は、非常に魅力的な制度ですが、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情です。その理由は2つあり、1つ目は申請しなければ受給できないこと、2つ目は経営者が助成金について多くの誤解をしていることです。そこで本稿では経営者が助成金についてよく誤解している8つの疑問にわかりやすく回答します。 -

金融機関との融資交渉で生まれる3つの副次的メリットとは?
経営者として金融機関から融資を受けることは、キャッシュの改善や信用力の増加など、お金の部分で多くのメリットを生みます。しかし、融資交渉を経験することは、事業に客観性と具体性が生まれ、相手の立場に立った説明が出来るようになるなど、お金以外にも副次的なメリットを数多く生み出します。 -

赤字に喘ぐ地銀が生き残り有望な中小の味方となる道はこれだ!
金融庁は直近発表した試算において、地方銀行の約6割は10年後に融資や投信の販売業務といった本業で、赤字に転落すると予想しました。地銀の統廃合は確かに進むのが当然です。しかし、大手企業への融資はレッドオーシャンで、望みは薄いもの。果たして地銀に生き残るための新たな活路はあるのでしょうか? -

ハッピー倒産ハッピー融資を実現する「経営者保証に関するガイドライン」を使い倒せ
2013年に金融庁が「経営者保証に関するガイドライン」を制定しましたが、その内容はまだ浸透していません。そのせいか、インチキ金融ブローカーが暗躍したり、制度をうまく利用できずに銀行との融資交渉を進められていない人が多いのも事実です。ガイドライン活用に向けた実践論を、経験豊富なキミアキ先生が解説してくれます。 -

東京大学が230億円のベンチャーキャピタル創設も資金の出元が残念すぎる件
東京大学が巨額のベンチャーキャピタルを組成しました。大学がベンチャーキャピタルを組成する意義は、母校を応援する卒業生が意欲有る学生や卒業生に投資をすることで、彼らの可能性を伸ばすことにあります。ところが今回のファンドの中身は過去の補助金、しかも出資はファンドというもの。メリットを感じにくいのが現状と言えます。 -

領収書を操作し会議費の要件を満たしても国税局が見逃さぬワケ
交際費には年間800万円の上限がある一方で、取引先との飲食で1人5,000円以下に抑えると、会議費に振り分けられ、上限無く損金とすることが可能です。これを利用して人数を水増しする悪知恵は、誰しもが考えるところ。ところが直近だと、積水化学工業は本件がバレて追徴課税を支払っています。なぜ会議費の不正操作はバレるのか?解説いたします。 -

社会保険の加入日を遅らせると倍返しで費用負担が増えるワケ
日本年金機構による社会保険調査の頻度が上がっています。調査の過程では、加入が適正に行われているか?支払いの元となる賃金が適正に申告されているか?加入日が遅れていないか?という3つの事項が主に調べられます。中でも加入日の遅れが生じていた場合、費用負担は倍増となるケースも生じます。適正な申告を心がけましょう。 -

崩れるか社会保険103万円の壁。共働き夫婦が今から備えるべきこと
安倍内閣の成長戦略のひとつに、女性の就業拡大があります。その一環として、「配偶者控除の見直し」が毎年のように議題に上がってきましたが、ついに実現に向けて動きだしそうです。今回のテーマは103万円の壁ですが、実はこの10月に130万円の壁も見直しが見込まれています。共働きと子育ての両立に向けて家族が備える時は「今」です。 -

経営者が消費者金融を資金調達で使うメリットはあるのか?
マイナス金利の導入により銀行からの融資が降りやすくなったと言われていますが、融資相談に数ヶ月の期間を要する場合もあります。その間に会社で入用となった時、消費者金融がパッと思い浮かぶ方もいることでしょう。そこで本稿では、経営者が消費者金融を利用するメリットとデメリットをご紹介します。 -

祝・広島カープ優勝!年間指定席を会社で買って節税対策
広島カープが25年ぶりにセ・リーグでシーズン優勝を果しました。ところで、プロ野球の年間指定席を会社名義で購入するケースはかなり多いようです。この場合、かかった費用はどのような名目で経費に算入すれば良いのでしょうか?目的別に変わる経費算入方法をご紹介します。 -

【必見】男性社員が育休を取ると会社が最大60万円もらえる「出生時両立支援助成金」
平成27年に男性の育児休業取得率は、2.65%と過去最高の取得率に到達しました。しかし、政府の目標とする男性の育児休業取得率は13%であり、目標には程遠い取得率です。そこで政府は今年、「出生時両立支援助成金」を新設し、男性に育児休業を取得させる企業へ最大60万円の助成金を出すことを決めました。詳細を解説いたします。 -

辞めた社員が同じ月内に転職したら厚生年金保険料を活用し節約
月初に入った社員が数週間で会社を辞めて、更に同じ月内に違う会社へ転職していたとしたら、経営者としては複雑ですよね。ただし、同一月内に社会保険の取得と喪失を繰り返した場合、最後に取得した被保険者分の標準報酬が年金額に反映されるため、前職の会社は厚生年金保険料の還付請求を行うことでお金が戻るので幾分かの節約が可能になります。 -

起業家の味方「新創業融資」を受けたい人が気をつけたい2つの点
創業時は実績がないため、貸す側に納得してもらえる収支計画を提出し、その計画が妥当だと判断されれば、融資をしてくれる可能性が高い時期です。日本政策金融公庫の新創業融資制度も融資要件が緩和されるなど、環境が充実しています。そこで、貸す側の視点から見て、融資交渉で気をつけるべき2つの点をご紹介します -

やり手FPが本音で語る!入院保険が必要な人と必要でない人
今や日本人の75%が加入している入院保険。本来は公的医療保険制度で医療費をまかなえるにも関わらず、曖昧な動機で加入して損をされる方も多いようです。そこで本稿では、やり手ファイナンシャルプランナーの赤井さんが、入院保険が必要な人と必要でない人について、ズバッと教えてくれます。 -

【2代目必見】会社を継いだらすぐ退職金制度をチェックしよう
終身雇用制が崩れ始めたとはいえ、依然として退職金制度は存在感を有しています。しかし、多くの会社では「先に金融商品ありき」で退職金の積立額が設定されているケースが多く、退職金の積立不足の放置が散見されます。支払い時に気がついたのでは時既に遅し。2代目社長は就任したらすぐに自社の退職金制度をチェックしましょう。 -

ディズニーに堂々と経費で行っても税務署を納得させる要件
どうしても仕事をしていけば多少の「グレーな費用」は良くある話なのですが、外部の人間から見ても「ムムムッ?」と思われるような支出は、誰から見ても怪しまれます。例えばディズニーランドに経費で行くとするなら、税務署はどのレベルまで経費算入要件を求めてくるのでしょうか?考えてみましょう。 -

【注意報】役員退職金の支払いに目をつける税務署を跳ね除けろ
創業から必死に会社を支えてくれた役員がいよいよ勇退する時、心ある経営者の貴方はできるだけ多くの退職金を出してあげたいと思うはずです。しかしながら、感謝の気持ちを込めて高い退職金を支払おうとする時ほど、税務当局は厳しいチェックを行い、延滞税や過少申告加算税を課そうとしてくるため注意が必要です。 -

法人の家賃を社長に支払うと節税や保険料負担の軽減が可能に
個人事業や小さな会社の場合、自宅を事務所に使っている方が多いはずです。ここに係る費用は経費として支出することが可能ですが、事業を株式会社などにすると、社長の自宅を事務所にしている場合、代表である社長に対して家賃を払うことが出来るようになります。 -

社員旅行・出張・接待でオリンピックへ行く費用は経費算入できるか?
いよいよ、夏期オリンピックがブラジル・リオデジャネイロで始まりました。治安問題を含め、日本人の観戦客にとっては不安要素も沢山ありますが、それでもオリンピックに行きたいという方は多いようです。そこで本稿では、社員旅行、出張、取引先の接待の3パターンでオリンピックへ行った場合の費用が経費算入可能か考えてみます。 -

「医療保険の法人契約」3つのメリットと2つの注意点
生命保険は、契約者・受取人を法人、被保険者を代表者にすることで、万が一の時に備えて、会社を守るための命綱として利用されています。そこで本稿では、社長の生命保険について法人契約を締結する3つのメリットと、注意しておきたい2つの点について解説いたします。