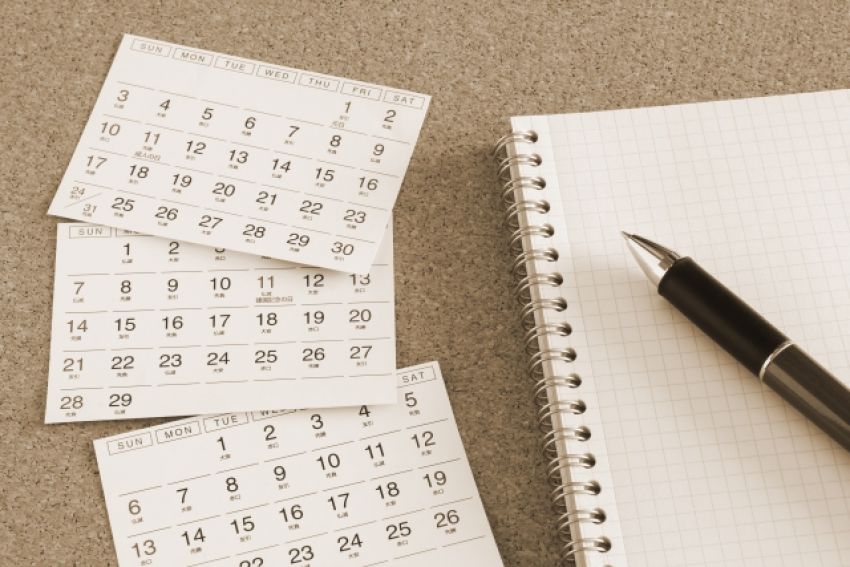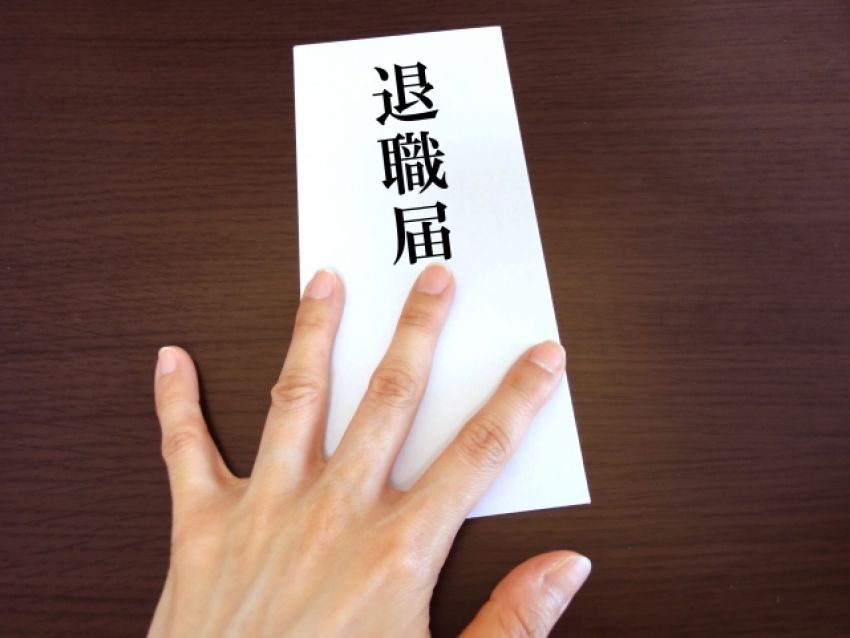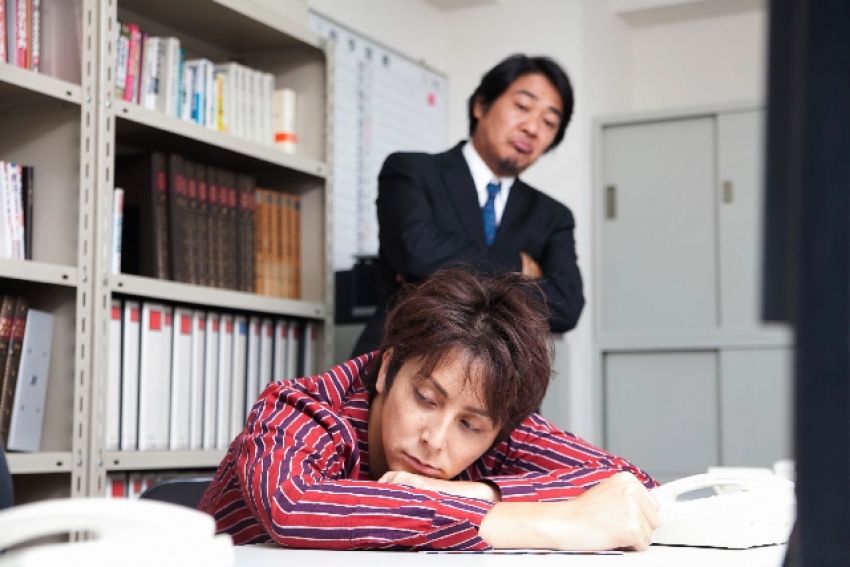松本 容昌– Author –
【業務内容】
お客様は、こんなお悩みや不安をお持ちではありませんか?
▼会社経営は初めてなので、労務管理のことが不安だ・・・。
▼従業員を雇ったら、何をすれば良いのかよくわからない・・・。
▼気軽に相談できる専門家がいない・・・。
▼助成金を活用していきたい・・・。
▼優秀な人材を雇用したい・・・。
当事務所では、ご相談には、開業15年、就業規則作成実績100社以上、助成金支給総額1億円以上の実績を持つ代表社会保険労務士が直接対応させていただきます。
こから起業する方や起業後間もない方は、馴れない事や不安な事が多いかと思います。
私は、これまで培ってきた経験やノウハウをお客様の事業発展に役立てたい、と同時にいつまでも経営者の方の心強い味方でありたいと思っています。
「従業員」に関するお悩みや「助成金」に関する疑問等、お気軽に何でもご相談下さい。
【経歴・実績】
1966年生まれ 静岡県浜松市出身
立教大学経済学部卒業後地元企業で不動産営業、保険代理店営業に13年間従事後。
平成11年社会保険労務士試験合格後、平成13年社会保険労務士事務所「オフィスまつもと」を設立。
開業後、一貫して労務コンサルティングと助成金業務を中心に業務展開を行ってきました。
多種多様な企業の様々な労務相談に応じており、数多くの労務トラブルの解決に尽力してきました。就業規則の作成実績数は、100社以上に及びます。
これまでの経験を生かし、
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則作成講座&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」
「パートタイマーの上手な活かし方」 等を多数開催。
☆主なセミナー実績☆
平成21年2月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 アイミティ浜松
平成21年3月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 浜松アリーナ
平成21年6月
労務管理セミナー
「パートタイマーの上手な生かし方及び助成金活用セミナー」 浜松まちづくりセンター
平成21年7月
労務管理セミナー
「会社を守るための就業規則&知らないと損をする労務トラブルを防ぐ5つのポイント」 富士交流センター
平成21年10月
飲食店で成功するセミナー 浜松市福祉交流センター
また、助成金業務に関しては、これまで取扱った助成金の種類は20以上で、申請企業数は100社以上に及びます。
特に、平成22年以降は、独立・開業時助成金を活用しての独立・開業支援を主力業務として、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県にわたって独立・開業支援業務を展開。
申請助成金額平成24年度は、2,000万円以上です。
☆助成金活用事例とお客様の声です☆
http://www4.tokai.or.jp/office.m/katsuyoujirei.html
また、独立・開業支援セミナーも東京都、静岡県を中心に多数開催してきました。
☆主なセミナー実績☆
平成22年2月 第1回独立・開業支援セミナー 静岡県教育会館
平成22年4月 第2回独立・開業支援セミナー 沼津市民文化センター
平成22年10月 第3回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成22年12月 第4回独立・開業支援セミナー 東京都豊島区市民文化センター
平成23年2月 第5回独立・開業支援セミナー 東京都江東区豊洲文化センター
平成23年4月 第6回独立・開業支援セミナー 東京都江東区商工情報センター
平成23年7月 第7回独立・開業支援セミナー 東京都江東区江東産業会館
☆マスコミ出演☆
平成22年1月29日 SBSラジオ「繭子の部屋へようこそ」
平成22年4月2日 SBSラジオ「第1回独立開業支援室」
平成22年5月21日 SBSラジオ「第2回独立開業支援室」
平成22年6月25日 SBSラジオ「第3回独立開業支援室」
-

パートタイマーやアルバイトと「雇用期間」を巡ってトラブルを起こさぬための対策
パートタイマーやアルバイトで、会社にとって十分な戦力として働いてくれる方が、貴方の会社にもいるのではないでしょうか?ところが不況の煽りを受ける等して、やむを得ずこのような方達に雇用期間の満了を理由に辞めてもらわねばならぬ時、その主張が通らない場合があります。どうしてそのようなことが起こるのか説明します。 -

取締役が兼務役員とみなされ雇用保険や助成金の対象となるため必要な2つの条件
法人の取締役であっても、労働者としての身分性が強い人は、労働者としての身分性が強い「兼務役員」とみなされ、雇用保険の適用を受けたり、助成金申請の頭数として数えることができます。しかし、兼務役員とみなされるには、1)労働時間が管理され、2)報酬では無く賃金が支払われている、という2つの条件を満たす必要があります。詳細を解説いたします。 -

ネットの普及前と後を比較すると労使トラブルは◯倍に増えている
36協定の見直しや、電通で起きた長時間労働・パワハラによる自殺により、労使トラブルに大きな注目が集まっていますが、現実としては相変わらず、長時間労働やパワハラ、それに不当解雇が、日常茶飯事で生じています。しかし、インターネット普及後に労使トラブルは5倍増となっており、経営者は労使トラブルを、より自分事と捉える必要に迫られています。 -

懲戒処分で唯一法律の制限がかかる「減給」その範囲はいかほど?
ある社員が致命的ではないにせよ問題を起こした場合、懲戒処分として減給を言い渡すことがあるかもしれません。ただし、減給には労働基準法で制限がかかっているため、就業規則における記載はもちろん、減給自体も適正に行わねば、かえって会社が訴えられることになり、注意が必要です。 -

変形労働時間を導入する企業は求人票の年間休日記載にご注意を
厚生労働省の有識者検討会は、民間の職業紹介事業者に対して、募集条件に虚偽の記載がある求人を出した企業と幹部に、懲役刑を含む罰則を設けるべき、という趣旨の報告書を提出しています。特に年間休日の記載は大きな誘引となるため、間違えが命取りになります。変形労働時間制の企業はもともと年間休日の計算に間違えが生じやすいため注意が必要です。 -

社員と会社間の解雇トラブルを防ぐため経営者に求められる2つの視点
解雇した社員から不当解雇で訴えられるニュースは後を絶ちません。世間から悪者にされるのはもちろん、長い裁判の過程は経営者を精神的に苦しめます。つまり、無用な解雇トラブルは一つの得も会社にもたらしません。どうすれば問題社員との間で無用な解雇トラブルを起こさずに済むのか?2つの視点をご紹介します。 -

トラブル社員が退職する際に必ず退職届を貰ったほうが良いワケ
勤務先の会社を社員が辞める時は通常、会社に退職届が提出され、基本的には本人都合の退職となります。社員との関係が円満であれば、トラブルが起こることはまず無いでしょう。しかしトラブル社員が退職届を提出せずに辞めた場合は、後にハローワークなどで問題が起こる場合があります。トラブル社員の退職時ほど退職届をもらう必要があります。 -

出向させた社員と派遣した社員で労災保険の扱いはどう変わる?
出向と派遣には、「出向:労働契約の一部又は全部が出向先に移る」「派遣:労働契約は派遣先には移らず、あくまで派遣先は指揮命令権のみを有する」という違いがあります。双方のケースで労災事故が生じた場合、労災保険の適用はどのように変わるのかご説明します。出向の場合は、労災保険の支払い負担を誰が行うかも変わるため注意が必要です。 -

トラブルが起きがちなアルバイトの有給休暇手続をズバリ解説
社員の有給休暇は月給制で賃金が支払われているため、あまり計算上のトラブルが生じません。対して、アルバイトさんなど時給制従業員の有給休暇は、時給制であることや働く日数が週に5日でないなどイレギュラーなため、計算が複雑になりがちでトラブルの温床となります。時給制従業員の有給休暇手続きについてズバッと解説いたします。 -

誤解の多い助成金:経営者が答えに詰まる8つの疑問に回答
助成金は、非常に魅力的な制度ですが、ごく一部の企業にしか利用されていないのが実情です。その理由は2つあり、1つ目は申請しなければ受給できないこと、2つ目は経営者が助成金について多くの誤解をしていることです。そこで本稿では経営者が助成金についてよく誤解している8つの疑問にわかりやすく回答します。 -

通常勤務でも深夜割増賃金が必要?!深夜割増賃金計算のワナ
経営者の方の多くは、10時以降に従業員が働く場合、深夜割増は単純に1.25割増しで良いと考えがちです。しかし、もし従業員が午前中から働いて、10時以降も働いている場合は、残業代と深夜割増賃金をダブルで支払わねばならず、1.5倍では済みません。長時間労働は労働基準法上でメリットが無い労働形態といえます。 -

社会保険の加入日を遅らせると倍返しで費用負担が増えるワケ
日本年金機構による社会保険調査の頻度が上がっています。調査の過程では、加入が適正に行われているか?支払いの元となる賃金が適正に申告されているか?加入日が遅れていないか?という3つの事項が主に調べられます。中でも加入日の遅れが生じていた場合、費用負担は倍増となるケースも生じます。適正な申告を心がけましょう。 -

今の36協定は何が悪いの?見直しが検討される理由を徹底解説
ついに厚生労働省が36協定の見直しに入ったことが、大きなニュースとして取り上げられています。36協定は特別条項を付与することにより、時間外労働の上限を会社が決められるため、長時間労働の温床と見なされています。しかし、上限に制限をかけたところで違う抜け道も…労務のプロが今回の動きを解説して下さいます。 -

辞めた社員が同じ月内に転職したら厚生年金保険料を活用し節約
月初に入った社員が数週間で会社を辞めて、更に同じ月内に違う会社へ転職していたとしたら、経営者としては複雑ですよね。ただし、同一月内に社会保険の取得と喪失を繰り返した場合、最後に取得した被保険者分の標準報酬が年金額に反映されるため、前職の会社は厚生年金保険料の還付請求を行うことでお金が戻るので幾分かの節約が可能になります。 -

社員からの「余った有給休暇」の買取請求に応じる必要はあるか?
日本の有給休暇の消化率の低さは大きな問題となっており、国策として有給消化率をあげるよう要請も提示されています。もし社員に余った有給休暇の買取を要求された場合、果たして会社側はその要求に従う必要があるのでしょうか? -

【2代目必見】会社を継いだらすぐ退職金制度をチェックしよう
終身雇用制が崩れ始めたとはいえ、依然として退職金制度は存在感を有しています。しかし、多くの会社では「先に金融商品ありき」で退職金の積立額が設定されているケースが多く、退職金の積立不足の放置が散見されます。支払い時に気がついたのでは時既に遅し。2代目社長は就任したらすぐに自社の退職金制度をチェックしましょう。 -

社員に損害賠償請求したらトンズラされた!給料差引きは可能?
従業員が重大な過失や故意の犯罪を起こした時は、信義則上で相当と認められる範囲で、会社が損害賠償金を請求することが可能です。ところが社員がこれを聞いて、いきなり会社をやめてしまったとしたら、この場合、手っ取り早く、従業員の給料から損害賠償金を差し引くことは可能なのでしょうか? -

「知らない」で済まされない!社員がうつ病になった時に社長が負う責任の範囲
経営者は労働契約上の義務として、従業員に対する安全配慮義務を負っており、従業員の心身の健康に配慮し、必要な措置を講じる必要があります。特に最近注目されているのが、社員のメンタル面まで健康状態に配慮することですが、どれくらいの責任を経営者は負わされるのか?最高裁の判例から提示します。 -

労働基準法が労働時間の規定に例外を設けている唯一の業界は?
「うちの業界は慣習的に労働時間が長い」「残業代を出さないのは、どこも同じことをやっている」という声が未だにあります。はたまた「うちの業種に限って例外規定はないのか?」と尋ねられる方もいますが、果たして労働時間や残業代は業種業態で例外があるのでしょうか?唯一例外規定の存在する業界はどの業界でしょうか? -

労災保険を使うと翌年の保険料が上がるって本当?
「労災保険を使うと労災保険料が上がってしまう」と考えている経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。確かに労災保険にも、給付された保険金の額を保険料に反映させる「メリット制」がありますが、これは「利用の有無」ではなく「従業員数」によって定められます。間違った知識を覚えると労災隠しに繋ることもあるため、覚えておくと良い知識です。