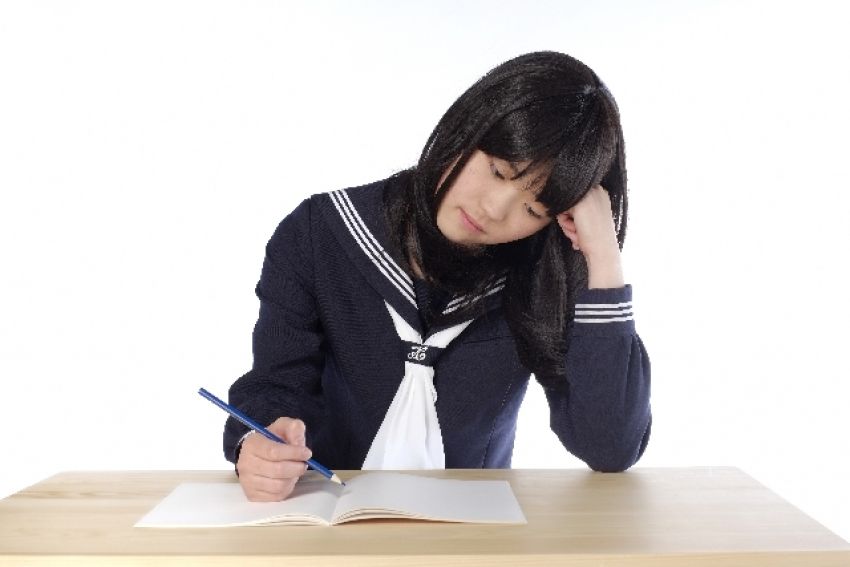大原達朗– Author –
一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会代表理事・アルテパートナーズ株式会社代表取締役として、M&Aを手掛ける公認会計士です。
BBT大学、法政大学院イノベーションマネジメント科の教員も兼任しております。
大企業だけではなく中小企業にとっても、ユーザーフレンドリーな会計業界を、世界中に広めることが目標です。
M&Aの悩み(会社や事業を売りたい/会社や事業を買いたい/小規模M&A投資を検討している)があれば、お気軽にお問い合わせください。
運営サイト:
経営者のための実践ファイナンス
【現職】
一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会代表理事
アルテ監査法人代表社員
アルテパートナーズ株式会社代表取締役
日本マニュファクチャリングサービス株式会社監査役
法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師
ビジネス・ブレークスルー大学大学院准教授
ビジネス・ブレークスルー大学准教授
PT. SAKURA MITRA PERDANA Director
【職歴】
1998年10月 青山監査法人プライスウオーターハウス入所
2004年1月 大原公認会計士事務所開設
2004年6月 株式会社さくらや 監査役
2006年1月 株式会社ライトワークス リスクコンサルティング部ディレクター
2007年4月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院講師
2008年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科兼任講師(現任)
2008年4月 アルテ公認会計士共同事務所開設 代表パートナー
2008年6月 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 監査役(現任)
2009年4月 アルテパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)
2010年7月 アルテ監査法人設立代表社員(現任)
2010年8月 日本M&Aアドバイザー協会 理事
2014年10月 日本M&Aアドバイザー協会 代表理事(現任)
2016年4月 ビジネス・ブレークスルー大学准教授(現任)
【所属団体】
日本公認会計士協会、一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)、日本税理士会、日本CFO協会
【資格】
公認会計士、税理士、 JMAA認定M&Aアドバイザー (CMA)
【その他】
ビジネス・ブレークスルー大学大学院MBA/経営管理修士(専門職) 日本CFO協会主任研究員(2006年)
-

旧村上ファンド系が東芝株を大量取得〜650億の投資を支える2つの材料
3月23日(木)に、旧村上ファンド系のファンドが650億円前後を投じて、東芝の株を8.14%取得したことが大きな話題となりました。この段階で債務超過に陥っている企業の株を取得することは、すなわち上場廃止、破綻の可能性がないと判断したと言って過言ではありません。彼らの意思決定を支える2つの材料をご紹介します。 -

市進HDが学研の持分法適用会社へ 学習塾業界でM&Aが頻発する背景
学研HDが市進HDの株を30%超まで買い増し、持分法適用会社とすることが報道されました。2015年には、Z会と栄光ゼミナールのM&Aも行われており、学習塾業界ではM&Aによる業界再編が進みます。これはつまり、業界が成熟産業となったことや、取引先や従業員に対して将来リストラが起こることを意味します。変わり続け、新しいものを生み出さねば残れない人が出て来るはずです。 -

糸井重里の「ほぼ日」が上場。メディアが語らぬもう1つの理由
糸井重里さんが社長を務める「株式会社ほぼ日」が3月16日に上場しました。報道の論調は上場の目的が、糸井氏頼みの「個人事務所」から、普通の会社になること、というものが主流です。たしかにこれも上場の理由かもしれませんが、おそらく今回の上場には、報道されないもう1つの狙いがあると思われます。それは相続対策です。 -

どうなる東芝?!現状を客観的に整理するとほぼ勝負ありなワケ
業績不振で揺れる東芝の救済策が連日のように報道されています。しかし、原発ビジネスの肝・ウェスティングハウスが法的整理に向かうことが報道され、状況は非常に厳しいところまで進んでいます。有力視されている産業革新機構による支援にも疑問符が付いており、客観的に見て東芝にはビジネスを継続しようにも何も残らない状況となる可能性が高まっています。 -

コスモ石油がキグナス石油と提携〜具体的な動きが無いM&Aは失敗の典型パターン
コスモHDがキグナス石油と提携すると報道されています。ところが、資本提携したにも関わらず、両者の具体的なシナジーが発揮される時期は3年後と遥か先の話。M&Aは様子見には不向きで、一気に企業を変える、変わるために有効な手法です。ビジネスデューデリジェンスの無いM&Aは失敗に終わりやすくなります。 -

ソフトバンクのスプリント株一部売却検討はM&Aの優れたお手本
ソフトバンクが2013年に2兆円強の大金を投じて買収したスプリント株の一部を、ライバルであるTモバイルの株主であるドイツテレコムへ売却検討しているという報道が先週されました。一部ではスプリントの売却劇を失敗とみる趣もあるようですが、その現実は実を取るための良策を取ったと言えます。M&Aは企業の目的達成と変化を成し遂げる手段に過ぎないからです。 -

キリンがコカ・コーラとの資本提携が頓挫したワケは一貫した基本方針が原因?
10月半ばに一部で報じられていた、キリンとコカ・コーラの資本提携が頓挫したことが、日経新聞によって報道されました。キリンのM&Aについては、過去にもサントリーとの間で「資本に対する徹底したマジョリティ取り」という今回と同じ方針が見られており、一戦略として理解できる部分はあるものの、手段が目的と化している可能性が見え隠れしています。 -

【失敗事例】キリンビールがブラジルでのM&Aで2,000億の損失!中小企業が学ぶこと
キリンビールが、2011年にブラジルでM&Aにより買収した同業メーカーを、トータル2,000億円の損失を出して売却する見込みである、と報道されました。金額の大きさは大手ならではのものですが、中小企業のM&Aにおいても今回の事例と同じ要因で失敗が起きます。今後、企業買収や事業譲渡を検討される方にとっては、貴重な教訓を与える事例です。 -

揺れる東芝が半導体事業の一部を売却〜分社への出資先が狙うのは◯◯
東芝が電力ビジネスの不振、投資先の「のれん」減損問題で揺れ、株価も12月5日の465円から、年明けの1月19日には243円へとほぼ半減するなど、早期の体質改善を求められています。そのような中で、報道は“虎の子”の半導体事業の一部売却を東芝が検討していることを伝えています。引受先候補のキャノンやファンドが狙う果実とは何なのでしょうか? -

ライザップがジーンズメイトを買収⇒ダイエットジムと全く関係無いのになぜ?
ライザップって何で稼いでいると思う?と聞かれたら、おそらく多くの人は、「パーソナルトレーニングジム」や「健食ビジネス」で稼いでいる企業だと答えることでしょう。しかし、ライザップが既に多くの買収を繰り返し、アパレルビジネスでも稼ぎ始めていることをご存知ですか?今週始めに発表されたジーンズメイトの実質的買収も、その一環で行われたものです。 -

アメリカ次期大統領・トランプ氏の会見後に株価が下がったのはなぜ?
今月の11日に次期米国大統領・トランプ氏の会見が行われましたが、政策の実現性に懸念が広がった結果、失望感によりNYダウが下落したことが報道されています。史上最大規模の雇用を生み出し、国内景気をあげる施策を打ち出したにも関わらず、その内容が市場に嫌気されたのはなぜでしょうか?その理屈を解説します。 -

新潟の第三セクターが運営するホテルを中国資本へ売却したのはなぜ英断か?
12月末に、中国資本の日本山嶼海(さんよかい)株式会社が、新潟県阿賀町100%出資の第三セクターにより運営されているホテルを買収することが報道されました。中国を始めとする外国資本にとって、日本は魅力的な投資市場です。一方で、国内では人種や国籍を一括りに、これら案件を潰してしまう例が多々見られます。取引は「国籍」ではなく「人」と行うものです。 -

KDDIはなぜ2年も待ってビッグローブをファンドから高い金額で買ったのか?
2年前にNECは、700億円でビッグローブを日本産業パートナーズへ売却しました。その2年後に今度はKDDIが、800億円で日本産業パートナーズから、ビッグローブを買収することになりました。KDDIは2年前に、NECから直接ビッグローブを買収することも出来たはずなのに、なぜ期間を置き、高い金額で買収することにしたのか?M&Aのプロが解説いたします。 -

日本企業が金融業で稼ぐ中、海外の企業が金融業からの撤退を始めている事実
日本を代表する大企業の多くは、本業以外に金融業で収益の屋台骨を支えている特徴を持ちます。対して、世界的な潮流としては、韓国のポスコやアメリカのGEに代表される世界企業で、金融業からの撤退が始まっています。20世紀は資本の時代であり、中でも金融業はその花形でしたが、彼らはその収益基盤の変化に気づいている可能性が高いと言えます。 -

10分1,080円のヘアカット専門店QBハウスが物価の高いNYに出店するワケ
1,080円でヘアカットサービスを提供するQBハウスが、ニューヨークに出店すると報道されています。物価の高いニューヨークで、国内では低価格のヘアカットサービスと認知されているサービスを提供することに、同社はどのような狙いを持っているのでしょうか?業績や株主遷移を踏まえながら考えてみましょう。 -

なぜトヨタは円高でも強いのか?海外進出した他企業との違い
為替の円高傾向が強いにも関わらず、トヨタの業績は上方修正されることが見込まれています。海外進出してもうまく行かず、多額の為替差損を計上している企業と同社の違いは、各国通貨による資金調達を可能にしているか否かに、一つの原因を見出すことが出来ます。海外進出の大原則は、「投資は株式で保有し子会社は資本で保有する」ことです。 -

味の素が“Blendy”の商標を259億で取得〜実質は節税を兼ねた高度なM&A
味の素が「Blendy」、「MAXIM」などの商標権を、オランダのジェイコブズ・ダウ・エグバーツ社から、259億円で取得すると報道されています。報道は同社がこれにより、マーケティングの観点で自由度が高くなることにフォーカスしていますが、実際にはもう一つの狙いがあると推測できます。それは、節税を兼ねた高度なM&Aを実現することです。 -

JR九州が上場にあたり変化させた財務体質と望まれる事業展開
10月25日にJR九州が東証一部に上場しました。公募価格2,600円に対して、初値は3,100円の値を付けて、上場企業としてまずまずのスタートを切ったと言えそうです。今回の上場にあたり、JR九州は民営化時から保有してきた資産の減損処理を一気に行いました。その背景には苦戦している鉄道部門の存在があります。 -

売上15億で利益が出ていない企業を30億円で買収した事例がM&Aのお手本なワケ
日本の中堅・中小企業を対象とした独立系M&Aアドバイザリー・仲介会社であるM&Aキャピタルパートナーズが、同業のレコフを買収すると報道されています。ところがレコフの売上は約15億強で利益もほぼ出ておらず、この買収にM&Aキャピタルパートナーズは30億円を費やしました。それでもこの事例がM&Aのお手本と言える理由を解説します。 -

老人は増えているのに介護ビジネスが儲かりにくいのはなぜか?
老人福祉・介護事業の倒産件数が、9月の倒産数で前年同期比35%増、年間倒産件数も9月の時点で最多記録を更新したと報道されています。日本国内の数少ない有望なビジネスに見えるにも関わらず、なぜ介護ビジネスは儲かりにくいのでしょうか?その理由を解説いたします。