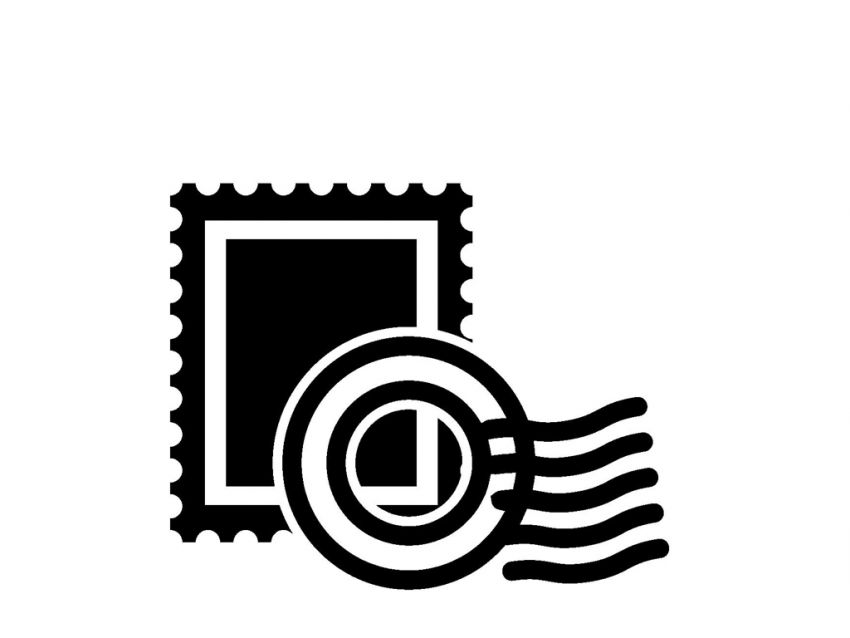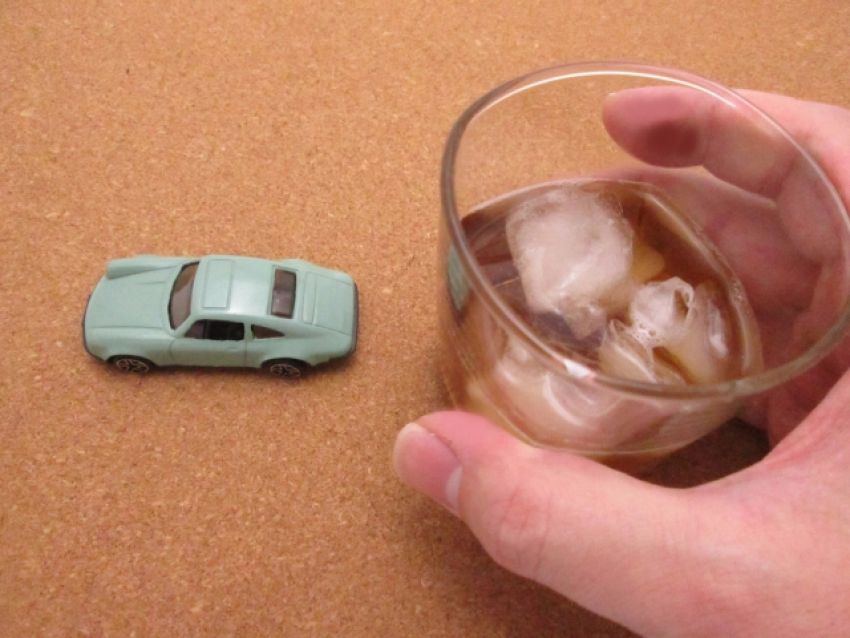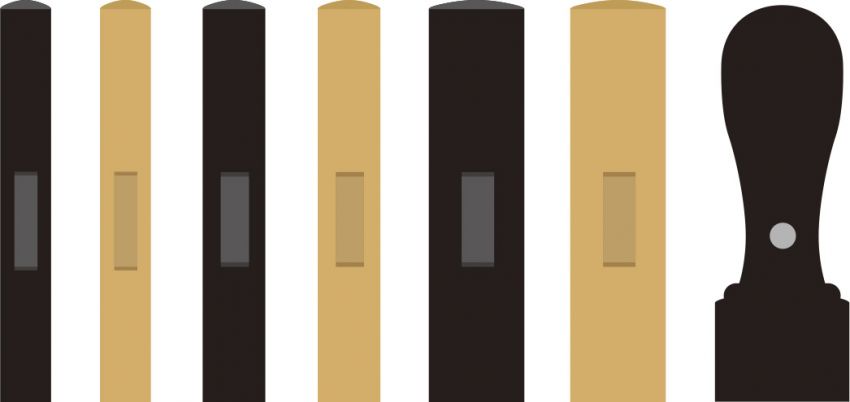行政書士 泉つかさ法務事務所– Author –
行政書士 泉 司 (兵庫県行政書士会会員)
京都府宮津市 1958年生まれ
京都産業大学法学部卒業
在学中は『司法研究会』に在籍。2年生からは選抜試験の結果『法職講座(上級)』として、教授および外部講師(弁護士)の特別授業を受ける。
卒業年に行政書士および宅地建物取引士試験合格。
卒業後10年間、民事専門の法律事務所(大阪市)に勤務し、民事訴訟全般の手続きを経験。
さらに企業内経験を積むため10年を区切りに一般企業へ転じ、注文住宅メーカー(営業本部・法務担当・上場準備委員)、コンクリート製品メーカー(広報IR・法務担当)、ソフトウェア開発会社(総務部長・管理本部副本部長)、貴金属リサイクル・産業廃棄物処理業(法務・M&A等)の上場企業勤務を経て、2012年3月、神戸市灘区に個人事務所開設。
開業後は、会社設立・法律顧問・法務コンサルティングのほか、個人のお客さまからのご依頼に幅広く対応。
数少ない廃棄物処理法の専門家として、遠方県の法人顧問を含め、地域を限定せず全国からのご相談に対応しています。
※行政書士のブログ 日々更新中
http://ameblo.jp/tsukasa-houmu/
-

産廃処理業者から5年分の支払請求を求められたが何年分まで応じるべきか?
建築会社を営んでいるAさん。建築会社の加工場ではいつも産業廃棄物が出るので、Aさんは適正にその処理を馴染みの業者Bへ委託してきました。ところが産廃処理業者Bに何度も請求書を出すよう依頼しているにも関わらずBは面倒くさがって、これを拒否してきました。そしてついにBは5年分の支払いを今年になって請求してきました。Aさんは何年分の請求に応じれば良いのでしょうか? -

「橋の下で拾った子供」がマジだった…「藁(ワラ)の上からの養子」の相続問題
「お前は橋の下で拾った子供だからか、本当に言うことを聴かない!」ほとんどの場合、この捨て台詞は親の冗談ですが、相続手続きの中では、出生した子を実の親の戸籍ではなく、別の人の戸籍に 「直接」その人の実子として届け出られる「藁(ワラ)の上からの養子」問題として知られています。トラブルが起こる理由、トラブルを未然に防ぐ方法についてご説明します。 -

美しい所作できれいな印影の印鑑を押す手順と正しい訂正印の押し方をおさらい
どんなに結果を出している経営者の方でも、印鑑を適当に押している人、訂正のマナーを知らない人を見ると、「この人は契約とか軽んじているのかな?」と思われる可能性があります。そこで本稿は、ご存じの方も多いかもしれませんが、美しい所作できれいな印影の印鑑を押す手順と正しい訂正印の押し方をおさらいします。 -

消印・割印・訂正印・捨印〜それぞれの意味と目的。気をつけるべき点
消印、割印、訂正印、捨印…印鑑を押すことには様々な名称があります。ところが、それぞれの意味や目的をいきなり聞かれると、なかなかはっきり答えられないもの。たかが印鑑の押し方ですが、取引の大勢に大きな影響を与える場合もあります。そこで本稿は、消印・割印・訂正印・捨印について、それぞれの意味と目的をご紹介します。 -

ガリガリガリクソン飲酒運転で逮捕〜酒席同席者に保護責任はあるか?
お笑いタレントの「ガリガリガリクソン」さんが、酒気帯び運転容疑で逮捕されたと報じられています。同じように、車を主要な移動手段とする地域では、未だに飲酒運転をする人が多々存在しており、これを看過する人、同乗する人もいます。果たして、逮捕された飲酒運転者と一緒にお酒の席に同席していた人には、飲酒運転者に対する保護責任が生じるのでしょうか? -

代表者印・銀行印・認印・角印〜会社で使う4つの印鑑・それぞれの用途は?
代表者印、銀行印、認印、角印…印鑑による押印で契約を成立させる日本では、会社に様々な印鑑が存在します。しかし、印鑑はそれぞれ持っているけれど、どの印鑑にどのような重要性があって、どのような場面で使えば良いのか?といきなり聞かれると、誰もが一瞬わからなくなるものです。そこで本稿は、法人が活用する4つの印鑑それぞれの重要性と活用場面をおさらいします。 -

正月の相続問題〜実家の墓や仏壇は本来誰が相続すべきか?
年末年始の帰省にあたっては親族が集まるため、相続問題について話し合われる方々も多いことでしょう。相続財産について誰が受け継ぐかを考える時、お金や不動産、株式はもちろんのこと、お墓や仏壇を誰が受け継ぐかも問題となります。お墓や仏壇の祭祀継承者は一体どのように決めれば良いのか?ご説明いたします。 -

ご存じですか?契約を有効にする収入印紙への正しい消印方法
収入印紙は、文書に見合った収入印紙を購入し、これを貼り、その印紙が二度と使えないよう「消印」することで、その税額を納めたことを証明する役割を持っています。契約を有効にする印紙の消印と、無効にしてしまう消印を知っていると、印紙代の無駄遣いをせずに済みます。 -

社長だった父が負債を抱えて死亡…負債相続時に気をつけること
父親が経営者である場合、莫大な財産の相続とは逆に、負債を相続しなければならない場合もあります。負債は勝手な負担割合の決定ができませんが、債権者との合意がある場合に、事業承継者が相続人全員の同意と署名捺印を元に、負債を受け継ぐことが可能です。しかし、全員の同意と署名捺印が無いと、相続が争続となる場合があるので注意が必要です。 -

【意外と知らない】記名押印・署名捺印で証拠能力が高いのは?
契約は一般的に、署名・捺印欄が用意されています。契約に合意したことを両者が表すことにより、法的な証拠効力が生まれますが、この欄への記入スタイルも様々存在します。印鑑とビジネスマナーの関連性も含め、果たしてどのスタイルほど証拠能力が高いのかご紹介します。 -

経営者の代表印が押印されていない契約書に効力はあるか?
法人の作成する契約書は一般的に、代表取締役(社長)が押印するものと考えられています。しかし、代表取締役が押印できない状態にある時でも、代表取締役の押印は必要なのでしょうか?意外と知らない印鑑トリビアを本日はご紹介したいと思います。 -

相続するはずの預金が無断で引き出された!どうすればいいの?
父の訃報を受けて、悲しみに暮れながらも、財産について遺産分割を話しあおうとしたところ…預金口座にお金が残っていません!なぜか?少し考えると「まさか、アイツ勝手に使ったな…」という人間がいたりします。もちろん相続財産の無断使用は不法行為なのですが、解決は一筋縄とはいきません。その理由を解説していただきます。 -

養育費の請求は誰の権利?支払いや受け取りに増減はあるの?
子供が生まれた後に夫婦が別れる時、大きな問題として噴出するのが「養育費」の問題です。そこで本日は、養育費の権利は誰に帰属するのか?支払いや受け取りに増減はあるのか?という、養育費の2つの問題について触れてみたいと思います。支払側が養育費の増額に備えて打っておくべき事前策もご紹介します。 -

「名前だけ貸して」に気をつけろ 名前だけ役員が抱えるリスク
従業員がオーナー社長や、知人などから「名前だけだから」と頼まれ、会社の業務にほとんど関与しない、いわゆる「名前だけ」の役員(取締役)になることがあります。認められた感じがして、少し良い気分になるかもしれませんが、すぐに承諾することには大きなリスクが着いて回ります。「迷惑はかけないから!」と言われても、即答することはお勧めできません。 -

契約書トリビア:署名と印鑑ではどちらに法的証明力がある?
契約書は一般的に「署名」と「捺印」がセットで行われます。それでは署名かハンコ、どちらかしか相手に証拠を契約書に残してもらえない場合があったとして、貴方はどちらを優先しますか?更に印鑑はデキる営業マンとデキない営業マンを分ける鏡とも言われます。どのような場面で、その境界が判明するのでしょうか?契約書の署名と印鑑にまつわるトリビアをご紹介します。 -

これ得!契約書を2通作成せず印紙税の費用を節約する方法
私達の多くは、契約書を2社間で作成する際に、各1通、計2通の契約書を作成して保管することを慣習としています。ところがこれは慣習であって、実際のところ契約書は1通だけ作成して、1通だけに収入印紙を貼り付けても法的に有効となります。つまり印紙税は双方の負担を半額にすることも可能なのです。印紙税を節約する方法について、注意点と共にお伝えします。 -

どんな相手でもお金の貸し借りで◯◯しない人に金は貸すな
親しい友人、尊敬できる人、信頼できる永年の取引先から、「お金を貸して欲しい」と言われた場合に、もしも貴方がお金を貸す場合、「借用書(証)」はきちんと書いてもらいますか?お金の貸し借りは、立派な契約行為であり、「ちゃんと借用書を書きます。」と自分から先に言って来ない相手へお金を貸すことは、控えるべきでしょう。契約書の作成とは商談の際にメモを取るのと同じくらい当たり前の行為なのです。 -

企業の魂を奪う麻薬のようなコンプライアンス違反慣れ
『コンプライアンス』とは一般的に「法令遵守」と訳され、企業が社会的な存在として、事業選択や環境整備を行う際の判断基準を担う概念です。「コンプライアンスなんかで会社は儲かるのか?!」という意見に対する明確な答えはありませんが、コンプライアンス違反に慣れることは企業の存続に大きな悪影響を及ぼします。もしも違反が見つかったなら問題を封じ込めず、早期対策を打つのが唯一賢明な手段と言えます。 -

契約書にケチをつける取引先…実は信頼に値するその理由
契約書を軽く見がちな人は多いですが、実はとても大事なものです。なぜなら一方にのみ有利な契約書の起案は、取引関係を悪化させてしまう可能性があるからです。こちらが作成する場合、相手先がどこに引っかかるかで、その現状を推し量ることもある程度はできますし、支払いにシビアな相手先は、決していい加減な会社でないことも確認出来ます。契約書を大事にしましょう。 -

民法第733条に設けられた「女性だけの“再婚禁止期間”」の趣旨
女性だけが離婚後6カ月間は再婚できないとする民法の規定は、「法の下の平等」などを定めた憲法に違反すると求めている裁判で、12月にも最高裁の憲法判断が示される見通しです。「女性にだけ再婚禁止期間が設けられているのは差別だ」という論点に注目が集まりますが、実際に733条の制度趣旨を冷静に見ると争うべき論点は「子供のためにどうなのか?」という部分に集約されるべきだとわかります。
12