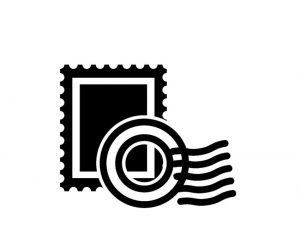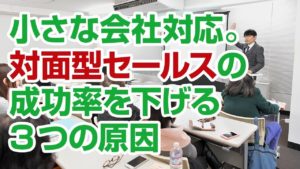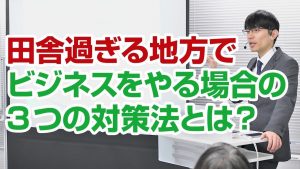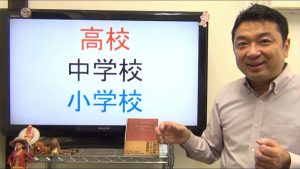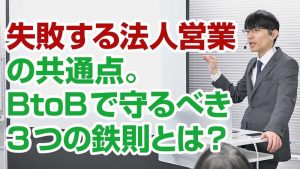法人の作成する契約書は一般的に、代表取締役(社長)が押印するものと考えられています。しかし、代表取締役が押印できない状態にある時でも、代表取締役の押印は必要なのでしょうか?意外と知らない印鑑トリビアを本日はご紹介したいと思います。
法人の契約は必ず代表取締役の押印が必要か?
契約書は、
- 商談を行ない
- 契約(書)の内容を合意し
- どちらかが契約書を起案し
- 当事者が署名捺印または記名押印する
以上の過程を経て、完全に有効な「合意文書」となります。
一般的に契約書は、「署名捺印」か「記名押印」のセットで表現されることが多く、信頼性が最も高いのは、署名で実印が捺印されているものです。
実印を要求される場合には、それが実印であることを証明するため、直近3ヶ月以内の印鑑証明書を添付することがあります。
法人は、代表者が選任される毎に、法務局に対して代表者毎の実印を届け出て登録する必要があります。
では、契約者として名前を表示し、印鑑を押すのは、誰が相応しいのでしょうか?
例えば、代表者が急病となり押印できない場合、海外へ代表者が出張中に急遽の契約が必要となった場合などは、対応に苦慮することが考えられますので、知識として知っておけば損はありません。
法人の契約に代表者の押印は必ずしも必要ない
個人の契約であれば、契約代理人がいる場合を除き、押印する人は当事者本人となります。
法人であれば、代表取締役(社長)が最も相応しいと言えますが、実際のところどうなのでしょうか?
実は、この代表者も「法人の代理人」ですから、ほかに法人の契約代理人として相応しい者がいれば、代表者でなくても構いません。
それぞれの担当に関する契約であれば、担当取締役、営業部長、総務部長、工場長、所長などでも構いませんし、普通に行なわれています。
ただ、相手方・外部の者からすれば、その押印者にその(社内規程上などの)権限があるかどうかなどは分かりません。
「決済権のある人間が押印していない契約書は無効とならないだろうか?」というリスクが頭をよぎることでしょう。
しかし、この点も法的に考えれば、その契約を締結する権限があるだろうと思われる者であれば、有効であると信じたことに過失はない、つまり契約書は有効に成立していると一般的には考えられています。
契約書が有効であれば、その効果は(その契約上の権利も義務も)法人に帰属する(生じる)ことになるわけです。
リスクを踏まえた印鑑の社内規定を整備しよう
これらのことを考えると、会社はリスクを踏まえて、安易に契約をしない・させない必要がありますし、印鑑(印章)は慎重に管理することが必要になります。
やはり、契約締結権限は、限られた者とする社内規程の整備、印鑑・印章の管理(規程)を整備することが、法人・組織を守ることになります。
「濡れぬ先の傘」ということわざがあるように、ビジネスの根幹を成す契約で失敗しないよう、前もって準備をしておきましょう。