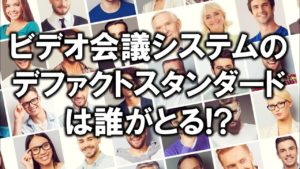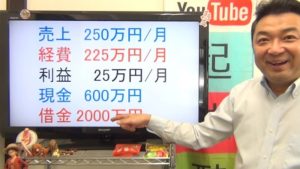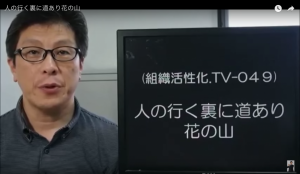ジョージ・クルニーが、テキーラ販売会社「カーサミーゴス」を1,000億円で売却することが報道されました。一般的なアルコールブランドは、長期的な消費者との信頼関係構築により、徐々に形成されていくのが一般的です。対して、同社は設立からわずか4年でトップブランドとなることに成功しました。これを支えたものとは何なのか考えてみましょう。
ジョージ・クルーニーがテキーラの会社を1千億円で売却するってよ
ジョージ・クルニーが、2013年にランディ・ガーバー(モデルで女優のシンディ・クロフォードの夫)と創業したテキーラ販売会社を1,000億円で売却すると報道されました。
売却する会社は、カーサミーゴスといい、短期間で全米屈指のテキーラブランドを作ることに成功しています。
ホームページを見てみると、以下のような感じです。

ジョージ・クルーニーのオーナー感が満載ですね(笑)
日本には、高級リカーショップ信濃屋の直輸入部門である田地商店を通じて輸入されていますが、1本が8,000円程度の上代となっており入手も非常に困難です。
カーサミーゴス社の短期間における成長を支えたもの
さて、今後もジョージ・クルーニーは、広告への出演などを通じて同社に携わっていくとしていますが、それにしても新規ビジネスを1,000億円で売却するとは凄い偉業です。
一般的なアルコールブランドは、長期的な消費者との信頼関係構築により、徐々に形成されていくのが一般的です。
対して、設立からわずか4年という短期間で、なぜこれほどのことを、カーサミーゴス社は成し遂げられたのでしょうか?
同社のテキーラはたしかに、毎年行われるコンテストにおいて入賞を続けるなど、その品質を評価されています。
それと同時に同社の躍進を支えている背景の1つに、コアターゲット層である若年世代へ、巧みなマーケティングでアプローチしていることがあげられるでしょう。
その最もわかりやすい例が、インスタグラムの活用です。
参考URL:casamigos/Instagram
ジョージ・クルーニーとランディ・ガーバーの2者による、熱烈なカーサミーゴス“推し”が伝わりますよね。
ちなみに、カーサミーゴスのインスタグラムアカウントには、なんと約85万人のフォロワーが存在します。
同じ酒類業界を見ても、アサヒビールのアカウント16.7万人、サッポロビールのアカウント15.3万人と比較(2017年6月現在)すれば、その規模は数倍に達しており、如何に設立当初からカーサミーゴスが、若年層を意識してSNSを活用してきたか理解できるのではないでしょうか。
効果的なマーケティングが競争優位性を作る
売れる商品を作り、効果的なマーケティングで売上を作り、一定以上のサイズになってから売却する、これはスタートアップの典型的な成功例です。
おそらく初めから売却を視野に入れていたのでしょう。
テキーラ自体に特別な競争優位性があるわけではありません。
カーサミーゴスは、ジョージ・クルーニーという強烈なアイコンを強みとして生かし、時流に応じた効果的なマーケティングツール(SNS)を活用することで、短期間のうちに売れるブランドを作ることに成功したのです。
今回の売却劇は、ITやAIがなくてもスタートアップはできるし、社会にインパクトを与えるようなビジネスを短期間に作ることは可能、ということを示す好事例と言えるでしょう。
日本でもこうした事例がドンドン出てきてほしいと心から思います。