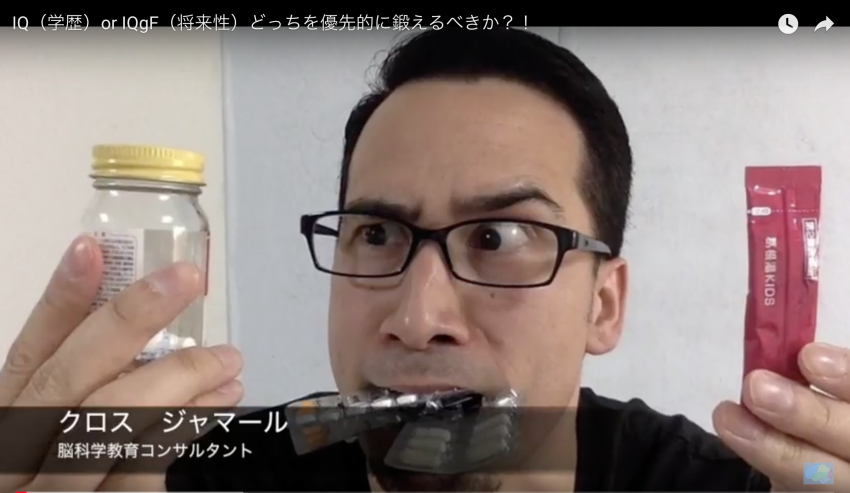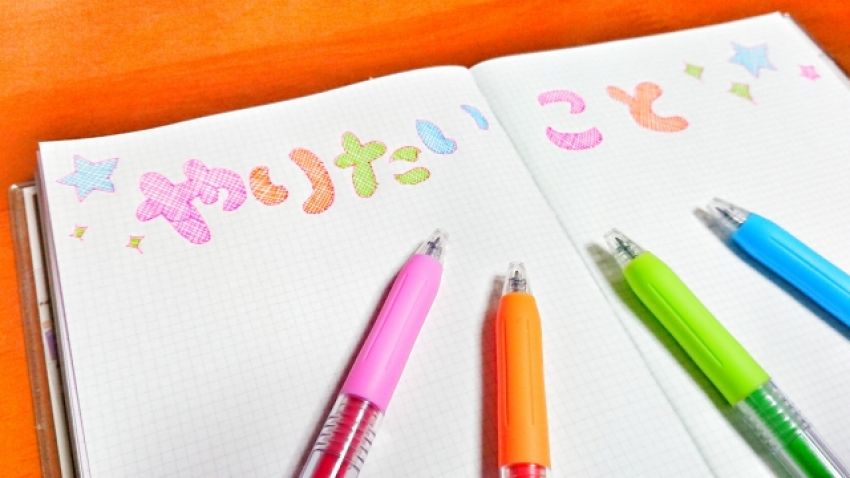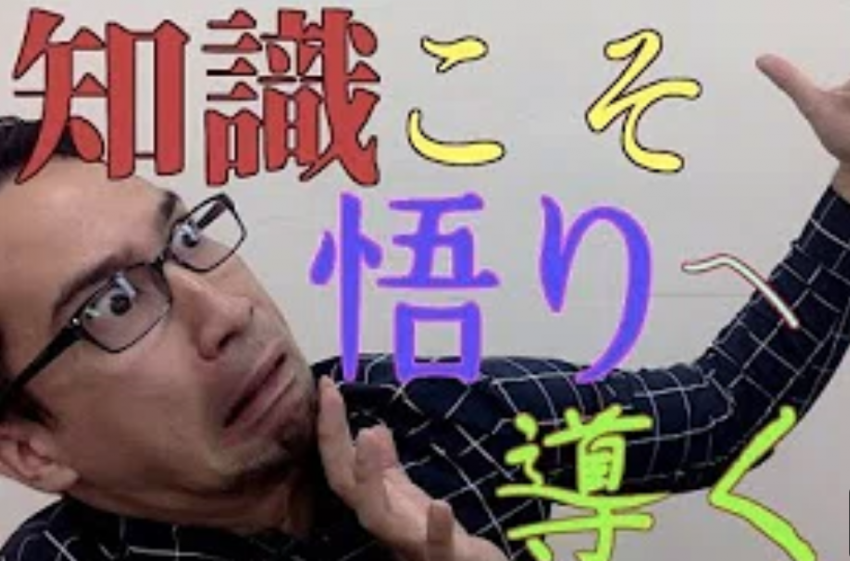Jamahl Cross– Author –
Jamahl Cross
Founder & Co-Director
一般社団法人脳科学幼児教育研究協会 理事
認知神経科学、脳リハビリ、発達精神病理学、進化心理学、発達障碍改善、認知行動療法など様々な分野を学び、実践を通じて統合する。独自の方法論に基づいた脳機能向上方法を編み出す。
企業脳科学、行動経済学、認知心理学によって解き明かされた非常識な企業成長法を提供。伸び悩んでいる企業を『平均利益率756倍の企業文化』へと変え、パフォーマンスを高めるなど数々の実績を持つ。
・社員のやる気を出させるのに苦労する
・昇給の効果に限界を感じている
・グループの能力を活かせずにいる
・目標が現状維持になっている
・批判しあう割には前進していない
・暴言や八つ当たりが目立つようになった
・ネガティブ思考が風邪のように流行っている
これらの問題は、それぞれ科学的なデータによって原因の特定、予測、予防が可能です。
数千に及ぶ論文を元に、経験のみに頼らないエビデンスベースドアプローチのリーダー育成を目指します。
コンサルティング内容の詳細、予約はこちらから
-

改善したい問題があるならフィードバックよりフィードフォワードを選べ
フィードバック、フィードフォワードは、2つともに何かを改善しようと思う時に行う作業です。ただし、フィードバックが過去の悪かった部分にフォーカスするのに対して、フィードフォワードは未来の自分に向けてフィード(ありたい姿)を投げかける作業です。この2つの作業は脳に全く異なる影響を与えます。できるだけ、フィードバックよりフィードフォワードを選んで欲しい理由もここにあります。 -

「高学歴あるいはIQが高ければ社会的に成功して幸せになる」はウソ
IQが高い人は高学歴、高収入で、家族とも幸せに過ごせていて、多くの人に役に立っているのか?自分の目標や趣味を大事にしているのか?というと、脳科学の世界ではあまり相関性が無いと考えられています。IQ以上にIQgを高めたほうが、前述のようなゴールも達成しやすく、IQも比例して高まりやすくなります。 -

「負の感情を表に出すな」と言われて育った部下や子供はチャレンジしなくなる
「ビビってはいけない」「怒ることはよくない」「イライラした表情を見せてはいけない」親であれ、上司であれ、このようなことを子供や部下に言い続けると、彼らはやがてチャレンジすることを恐れるビビリな人間となってしまいます。そうならぬために、上司や親はどのように彼らを育てればよいのでしょうか? -

あなたを批判する人の心理を知れば、100人中16人に好かれただけで幸せになれる
「お前は人間として未熟だ!」「お前は社会をなめている!」「◯◯になろうなんておこがましい!そもそも、お前は1人で生きてきたわけじゃないんだ!」こうやってあなたを批判する人達はどんな心理状態なのでしょうか?一方で、今のあなたを積極的に応援してくれる人もいるはずです。あなたが注目すべきはその人達。100人中16人に好かれただけで、あなたは幸せになれます。 -

理想の高い40代婚活女性に告ぐ。そのまま進め!バカにする奴は一切無視
40代の婚活女性が、結婚相手に「20代」「イケメン」「非常に優しい」「浮気をしない」「仕事をバリバリ働いて、年収は一千万円以上ある」「子育ても積極的に手伝ってくれる」という条件を求めているとしたら、あなたはどう感じますか?もしあなたが女性の立場にいたとしたら?実は、その理想の高さ、全然ありなんです。 -

ひがみ・悪口を言いたい人、それを気にせず無視する人の間に生じている差
ネットではよく、芸能人や有名人に対して、ひがみや悪口、ねたみ、最悪なケースだと殺害予告までしてしまう人を見かけます。これら、人を貶める行動はコンフォートゾーン(その人にとって居心地の良い場所)と密接に関連しています。ひがみ・悪口を言いたい人、言われても気にしない・無視する人、その差はどこにあるのでしょうか?どうすれば、ひがみや悪口を言わずに済むのでしょうか? -

他人に与えられた自信は弱く脆い 本当に強い自信はどうやったら付くのか?
他人から高く評価されると、自信が湧いて、一瞬嬉しくは感じるかもしれません。しかし、その後、同じことについて低い評価を受けるとどうでしょうか?あれほどあった自信が瞬間で萎むのを感じることでしょう。他人から与えられた自信は弱く脆いものです。どうすれば本当に強くて大樹のように根ざした自信をつけることができるのでしょうか? -

できる社長ほど愛人を作らないのはなぜか?脳科学の視点から答えよう
今日のテーマはズバリ「経営者と愛人」の問題です。脳科学の世界では、『できる社長はなぜ愛人を作らないのか?』という問いに対する1つの答えが出ています。脳科学教育コンサルタントのクロスさんによる解説です。 -

自己評価が低いとワクワクするゴールが見つけにくい 自己評価を高める具体手法
あなたは、本心から「自分なんか滅相もない」「いやいや、自分は何もしていないんですが」と言うタイプの人ですか?もし、その言葉が単なる謙遜ではなくて自己評価が低いので発するものなら、自己評価を高める必要があります。なぜなら、自己評価が低いと目標やゴールが見出しにくいからです。自己評価を高める具体的な手法をご紹介します。 -

叶えやすいゴールと叶えにくいゴール〜モテたい?金がほしい?ならこうしろ!
人はどうしても自分のゴールを設定する時に、「自分のために〜なりたい」と、自分の『Want to』が強すぎるゴール設定を行いがちです。しかし、このような感覚で設定するゴールは、実は小さすぎたり、上手くいかないケースが多いもの。どうすれば、自分の『Want to』をうまいこと維持しながらも、更にでかいぶっ飛んだゴールを設定し、達成することができるのでしょうか? -

「感謝引き寄せの法則」はオカルト?!お前の正体を脳科学の視点で丸裸にしたる!
「感謝で引き寄せの法則」は、多くの人が信じているものの、なぜか怪しい、とっつきにくいと毛嫌いする人も多い概念ですよね。そこで、本稿は脳科学教育コンサルタントのクロスさんが、脳科学の観点から、果たしてこの法則を活用すると脳にはどんな作用がはたらくのか?それはよいものなのか?ということを解説してくれます。 -

教養の無い人は、何を言ったかではなく誰が言ったかで判断する
「お前、過去散々こんな心配させたくせに」「お前、昔は、あーだったくせに」「何お前なんかが偉そうに言ってるんだ」と他人から言われたことはありませんか?教養のない人は他者の主張、その本質的な内容にフォーカスできず、その人の過去の言動とこれをごちゃ混ぜにして理解しようとしてしまいます。 -

自分がミスしたら『自分を許すvs自分を鼓舞する』どちらを選ぶ?
誰でも失敗すること、ミスすることはあります。では、失敗した時に『自分を許す』のか、『自分を鼓舞する』のか、どちらが良い選択となるのでしょうか?あるいは、許すのも鼓舞するのも両方ありだとして、使い分けの方法があるのであれば、どのような使い分けができるのでしょうか? -

『個性』と『協調性』を両方伸ばすと、本当に自分のやりたいことが実現する
『個性』と『協調性』は一般的に対立する概念として捉えられています。しかし、両者をどちらも伸ばすことで、私達は良い未来を選ぶことが可能です。本当に好きなことを始めた後でも、1人の『個性』に限界があると知れば、人は『協調性』を伸ばして、圧倒的な成果を出すことができるようになります。 -

【顧客やファンは俺が選ぶ】『Want to』じゃない仕事は今すぐ辞めろ
「やらなきゃ。仕事だからね。」「生きていくためには嫌な仕事もやらないとダメだよね。」もし、あなたがそう考えているなら、とてももったいないことです。『Want to』な仕事をする先には、あなたが選んだファンや顧客、そして協力者が待っているからです。現状を失う怖さと引き換えに得られるものは何物にも代えがたい人生の充実感です。 -

「こいつ、有能だぞ!」と思われるのは貴方にとって困難な返事をするタイミング
誰かが貴方にとって「んー、それはちょっと難しいな」とか「色んな課題があるな、どうしよう」と考えさせるような案を提示してきた時は、貴方が「こいつ、有能だぞ!」と思われる良いチャンスです。どのような返事をすれば、相手は貴方のことを有能認定してくれるのでしょうか? -

7年で利益を2倍押し上げたAir New Zealand社が取り入れたコーチング手法
2009年頃まで強く影響を残したサブプライムローンによる経済危機の煽りを受けて、Air New Zealand社の業績はもろに悪化していました。社員の多くは業績悪化を受けてマイナスのマインドを持つようになっていました。しかし、同社の業績は7年で純利益ベース2倍まで回復していきます。なぜ彼らは変われたのでしょうか? -

嫌なことをすぐ忘れ、くよくよしない「トリ頭」を持った人間になる2つの方法
あなたの周りには嫌なことをすぐ忘れられて、いつもニコニコしている、頭の切り替えが早い人はいませんか?実はこのようなタイプの人は学習能力が高く、非常に高い脳機能を持っている人です。逆にあなたが、いつまでも根に持つ、くよくよしやすい人であるならば、ある程度の訓練を経て、状態を良くすることがオススメです。 -

他人に謝れない、感謝できない人の思考回路や脳機能はどうなっているのか?
あなたの周りには、何かしてもらっても「当たり前」な感謝のない態度を取ったり、自分が悪くても心から謝れない人がいませんか?実は、このような人たちの行動は、脳科学で「なぜそうなるか?」を説明することができます。謝れない、感謝できない人の思考回路や脳機能はどうなっているのでしょうか?どのように彼らは改善を図っていけばよいのでしょうか? -

集団に所属しているだけで気持ちよくなるのはなぜか?集団心理の活かし方
集団に属している時、チームに属している時、人が気持ちよく感じるのはなぜでしょうか?集団に属していることが行動をエスカレートさせ、一人ではやれないようなことを、良い方向でも、悪い方向でも、やりのけてしまいます。その時、脳内ではどんなことが起きているのか?集団心理を上手く生かすにはどうしたら良いのか?ご説明します。