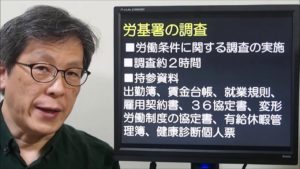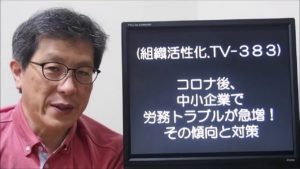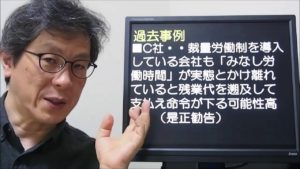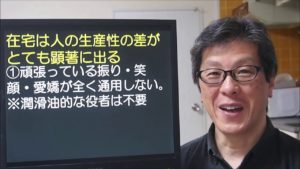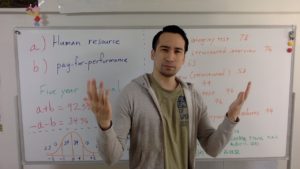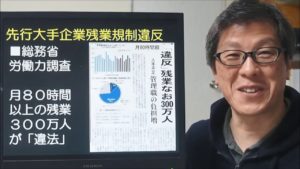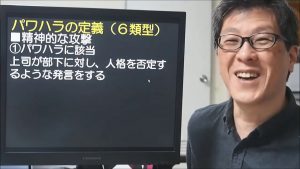事業を運営していると、社員に動いてもらう度に、事務用品、コピー、ノートパソコン、職種によっては制服代、防具など、様々な備品費用が発生します。会社側は、社員が使う備品の費用をどこまで負担する必要があるのでしょうか?労働基準法と労働契約法に照らし合わせて解説致します。
会社は社員が使う備品をどこまで負担すべき?
業務を行っていると何かと備品にお金がかかります。
文房具などの事務用品、コピー、ノートパソコン、職種によっては制服代、防具なども必要になります。
社員にとってみれば、業務に必要な費用は会社が負担するのが当たり前、と考えるのが一般的でしょう。
果たして会社側は、社員が使う備品の費用をどこまで負担する必要があるのでしょうか?
判断は会社毎でOK⇒範囲を決めた後は就業規則に必ず記載
結論から言うと、備品の購入範囲について社員にどこまで負担させるかは、その会社毎で判断して良いことになっています。
労働基準法は、備品の購入代金のどこまでが社員負担で、どこからが会社負担かを明確に規定していないからです。
たとえば、業務で使用するノートパソコンの購入代金を、会社が負担するか、従業員が負担するかは、会社の裁量で決めても問題ありません。
ただし、備品の負担範囲について明確な線引をするのであれば、労働契約法第7条に基づき、就業規則に必ずその範囲を記載しなければなりません。
第七条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。
また、労働基準法第16条には、
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
という文言で、ノルマが未達成な場合にペナルティを支払わせることを禁止してますが、この契約にはもちろん備品が含まれています。
つまり、「会社で一旦パソコンを買っておくが、ノルマが達成できなかったら自腹」などはNGです。
会社によって負担すべき最低限ラインは変わる
現実のところ業務に必要な備品は、会社が「最低限」負担しているのが実情でしょう。
なぜなら、その費用は収益を得るために必要な経費のはずだからです。
たとえば、IT企業ならばノートパソコンを頻繁に使用するため、ノートパソコンの購入費用を会社が「最低限」負担していることが多いでしょう。
一方で、飲食業を運営しているならば、制服の支給(貸与)が最低限の備品負担となっている場合が多いです。
従って、この「最低限」の負担ラインは、会社の財務状況や関わる業種業態、会社の実情に即して慎重に決める必要があります。
変な出し惜しみをすれば、労働力の酷使とみなされ、モチベーションも下がってしまいますし、非常に繊細な判断が必要とされます。