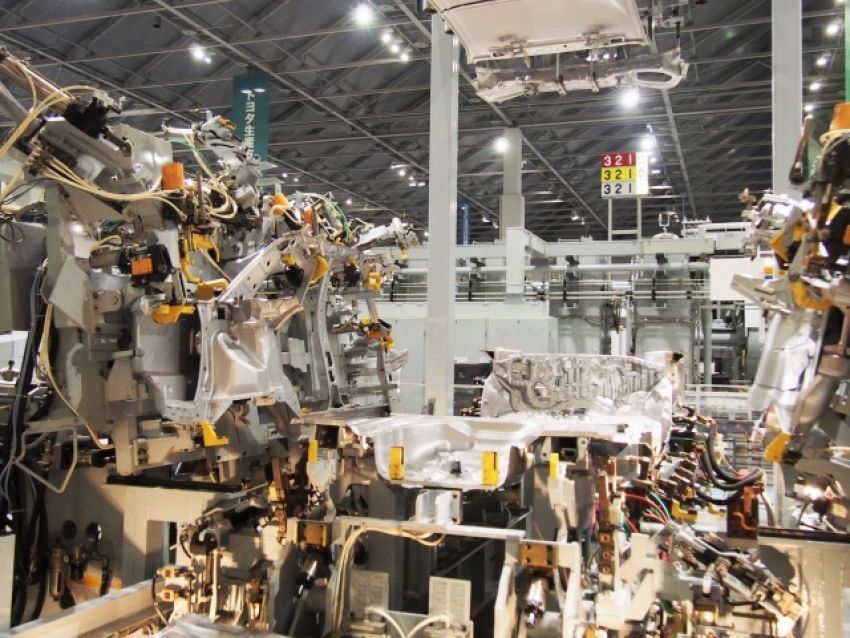株式会社IPMaacurie– Author –
株式会社IPMaaCurieについて
皆様は「知的財産」と聞いてどういうことをイメージされるでしょうか?
「特許も知的財産だよね。特許は取ったけど、経費ばかりかかって全然使い物にならないんだよね・・・」
「知的財産なんて、技術者やデザイナーが持つものでしょ?
営業とは直接関係ないし、まして経営には無関係だよね・・・」
「特許とかって、なんだか難しくて、よくわからない・・・」
いろんなイメージをお持ちかと思います。
弊社がお伝えしたいのは、「特許・意匠・商標などの知的財産は、使いこなすことによって会社の大きな収益源となる」ということです。
当社は、「知的財産・マーケティング・マネジメントを融合し、ライセンスによる収益を恒常的に得る仕組を創ることによって、中小・中堅・ベンチャー企業を元気にし、新たなステージへ導く」ことに特化した、日本で唯一のコンサルティング会社です。
わずか10回のコンサルティングで、御社の「見えない有益資産」である知的財産を見える化し、将来、億単位の収益向上に繋がる新たな収益力を引き出す独自の仕組が出来上がります。
これによって、御社は新たな収益源を得る異次元のステージに達することになるのです。
是非、出会いましょう!
是非、一緒に新たな発展のステージに進みましょう!
代表取締役 後藤昌彦プロフィール
1963年3月 大阪生まれ。
小学生時代は気の弱い泣き虫で、度々先生を困らせた「クラスの問題児」であったが、ある教師との出会いと指導をきっかけに立ち直る。
大阪大学大学院工学研究科修了後、象印マホービン(株)に入社。研究・開発部門での新商品開発業務を経て、35歳のときに知的財産担当となり、15年間にわたり研究開発・マーケティングと直結した知的財産権(特許・意匠・商標)の取得、活用、ライセンス交渉業務に従事。年間平均50件以上の特許出願と権利化業務をこなし、商品化において採用された特許は300件を超える。また、大手電機メーカーとのライセンス交渉にも携わり、電気製品では会社初のライセンス料獲得に成功する。
このような経験を通じて、「企業を持続的成長に導く収益向上戦略を実現する上で、確固たる知的財産活用方針の構築と実行が不可欠である」ことを体感する。
2013年に退職し、大阪の製剤系ベンチャー企業にて1年間の知財業務を通じ、中小企業の現場を体験する。
2015年3月に独立。現在は日本で唯一の「知的財産を活用して収益向上に結び付ける仕組み創りのコンサルタント」として精力的に活動。
保有資格 : 弁理士(特定侵害訴訟代理付記登録)・中小企業診断士
-

知財取得のスピードとビジネスのスピードに生じる差を埋める4つの方法
通常、知的財産は出願してから権利を取得できるようになるまで、長時間が必要となります。かたやビジネスや研究開発は日進月歩、明日はどうなっているかもわからないほどのスピードで進展します。どのような手段を講ずれば、知財取得をビジネスの戦略に組み込むことができるのでしょうか?4つの柔軟な方法をご紹介します。 -

見えぬ資産を見える化して顧客価値を生み出せ〜富士フィルムの好事例
知的財産は非常に概念的でわかりにくい企業資産であり、一見すると価値が無いように思える技術や仕組みの中に、それらの見えない資産は眠っています。しかも、私達は見えない資産を見える化して、競争力の源泉としなければなりません。これに成功した富士フィルムの事例を見ながら考えてまいりましょう。 -

日進月歩のソフトウェアと牛歩のハードウェア、特許を取るべきはどちら?
特許を取得する際には必ずコストが発生するため、収益に結びつかないものはなるべく特許を取得しない必要があります。このように特許の要・不要の見極めは非常に重要な意思決定ですが、技術内容や業界によって判断の善し悪しは様々に変化します。日進月歩のソフトウェアと牛歩のハードウェアを例に、どちらが特許を取得すべきパターンか考えてみましょう。 -

ジャイアンがすぐ殴るようにすぐ訴訟に訴える会社は負けやすい
せっかく時間とお金、そして手間をかけて自社が開発した技術やサービスをライバルに真似されるのは、あまり気持ちの良いことではありません。しかし、自社の権利を勝手に使われていることがわかっても、すぐ訴訟を起こすことは、自社の立場をかえって危うくする場合があることを認識しなければ経営は傾いてしまいます。 -

下町ロケットの一歩先を行く特許を利用した大手との付き合い方
下町ロケットで佃製作所は帝国重工へ特許の使用実施権を付与しました。もう一歩進んで考えると、実用的な特許を保有している場合、実施権のうち「販売」だけを大手企業に認める特許の利用方法があります。中小企業の悩みは販路の少なさであり、販路を持っていても技術を持たない大手企業があれば、両者の親和性が高い組み方となるからです。 -

凄いアイデアが浮かんだ!これ、特許を取ったほうが良い?
私達はときにアイデアベースで「世界を変えるかもしれない」凄い発見に出会うことがあります。この際によくあるのが、アイデアを特許で守ろうとする行動です。しかし、特許になるアイデアと商品化できる技術は必ずしも一致するものではないため、無駄骨となる場合があります。特許は形があってはじめて、有効活用が可能な武器となります。 -

知的財産を持つなら金融機関と事業性評価を通じた連携を取ろう
知的財産を持つ企業にとって、金融庁が金融機関に対して事業性評価を行うよう通達している今はチャンスです。多くの金融機関、特に地方銀行や信用金庫において、知的財産による事業性評価を行う機運が高まっているからです。資金調達以外にもビジネスマッチングをはじめ、金融機関との付き合いにはメリットが生じます。 -

コカ・コーラはなぜコーラの製法について特許を取らないのか?
多くの企業では、「知的財産は特許を取れば守れる」と考えられています。ノウハウのまま社内に抱えていてはダメだという声も多いようです。しかし、特許は取ると同時に公開されるのが原則であり、特許を取ることはライバル企業との争いが始まることを意味します。特許とノウハウを全く別物として切り分けて考えることにより、知的財産は守られます。 -

対法人から対個人へ領域拡大しても上手く行かぬ企業の共通点
BtoB(対法人)ビジネスをされてきた会社の多くが、BtoC(対個人)へビジネスの領域を広げようとしているのに、なぜか上手く行きません。その理由は、売る相手、ニーズ、売り方、全てが変わるのに、自分達の製品開発やマーケティング視点が、昔の顧客との取引延長線上にあるからです。 -

企業のブランディングに成功した経営者が共通して行うこと
激化する価格競争に巻き込まれず、独自の市場を作るために、昨今、中小企業においても「ブランディング」を行うことが、非常に重要視されはじめています。ブランディングを行う上で重要な要素は幾つかありますが、最も重要な要素は「人」であり、特に経営者自身が企業の広告塔となることが最も効果的です。 -

知的財産を利用して大手企業と組む前に用意しておきたいこと
中小企業が知的財産を有効活用する際は、大手企業と組むことが効率的な場合があります。しかし、いくら知的財産を持っているとは言え、経営資源豊富な大手と組む場合は用意周到である必要が生じます。相手の方が一歩も二歩も先手を打っていると考えられる場合、中小企業はどのような手を打つべきでしょうか? -

下町ロケットは知的財産の現実的で賢明な活用方法を伝えてない
昨年末の大ヒットTVドラマ「下町ロケット」は、主人公達が特許を真似した企業を相手取り、訴訟も辞さず、徹底抗戦の構えを取った痛快劇でした。ところが、現実の世界において、彼らのような行動を取ることは非常にシビアで、困難を極めます。特許を真似してくる相手と、どのように関われば、知的財産を最大限活用できるのでしょうか? -

中小企業のブランディング戦略と知的財産は切っても切れぬもの
大企業は多額の広告宣伝費を使って、CM等でキャッチコピーを利用した「イメージ戦略」を展開しています。ところが、そもそも企業名や著名なブランドを持っていない中小企業の場合は、同じようなブランディング戦略(イメージ戦略)を実行しても全く意味がありません。そこで中小企業にとって有効になるのが知的財産を活かしたブランディング戦略です。 -

知的財産を無駄にしてしまう企業と活用できている企業の違い
知的財産の特許を取るための初期投資と維持費用は、外部に委託すれば100万円は下りません。ところが、知的財産を活用しきれておらず、むしろ費用を無駄遣いして、勝手に「特許は無駄」と考える社長さんが多いようです。知的財産を無駄にしてしまう企業と活用できている企業の違いは、どこにあるのでしょうか?