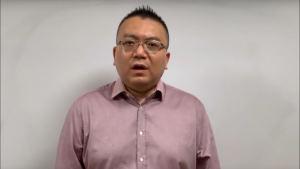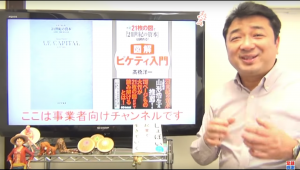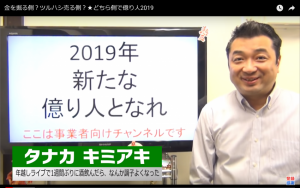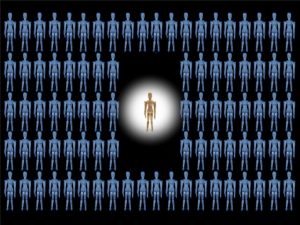社長の退職金積立は共済と保険どちらから始めたら良い?
社長もある程度の年齢になってくると、そろそろ後進に道を譲って悠々自適に暮らそうと考える人も増えてきます。
社長が辞める時に悩ましい問題が退職金です。長い期間務めていて辞めるのであれば、まとまった金額が必要ですし、突然会社から退職金名義でお金を抜けば、特に中小企業などは資金繰りが厳しくなってしまいます。
そこで社長は将来のことを考えるなら、会社をはじめて軌道に乗り始めたと同時に、自らの退職金を会社の財務に影響が無いよう、計画的に積み立てなければなりません。
代表的な政策としては、民間の保険を利用する場合と、公的機関が用意する共済を活用する場合があります。
それぞれにはどんなメリットやデメリットがあり、どちらから始めるのが良いのでしょうか?
民間の保険に加入するメリット・デメリット
将来の退職金支払いに備えるものとして、民間の保険を利用する場合があります。
逓増定期保険や長期平準定期保険などがよく使われますが、養老保険を使うこともあります。
保険は通常、年齢とともにリスクが増加することから保険料も増加していきます。これを保険期間通期にわたって同額とするのが、逓増定期保険や長期平準定期保険です。
後年増加する保険料を先に払っておいて、その分後々の保険料は増加しないという性質ですので、会計上、保険期間の途中までは前払保険料が発生し、ある期間を過ぎるとその前払保険料を取り崩していく、ということになります。
これらは節税対策とセットで導入されることが多く、ハーフタックスプラン(半額損金、半額資産計上)と呼ばれることもあります。
経営者は基本的に定年が無いため、辞めるまで長期にわたることが多くなります。
それに合わせて保険期間も長くなり、途中で解約すると解約返戻金(前払分の戻り)が返ってきます。この解約返戻金が最も多くなる年齢に退職期を合わせると、退職金の資金を確保できるという仕組みです。
この保険の注意点は資金繰りです。退職金の資金繰りのために入るのですが、前述のとおり期間が長期にわたり、その期間ずっと保険料を払い続けなければなりません。
もし支払が苦しくなって初期に保険を解約してしまうと、解約返戻金はほとんど戻ってこないまま、損をするだけで終わってしまいます。
解約時にいくらもらえるかだけでなく、毎年払っていけるのかも考える必要があります。
倒産防止共済に加入するメリット・デメリット〜保険と共済どちらから始める?
保険に近いものとしてあげられるのが倒産防止共済です。文字通り連鎖倒産を防止するための共済なのですが、掛金が全額損金算入できることから節税目的でもよく使われています。
上記の保険と違い、40カ月掛けると任意解約でも掛金全額が返金され、それ未満の期間でも解約時に戻ってくる率が高めに設定されているほか、掛金が上限に達しても解約せずそのまま据え置くことができます。
ただし、掛金総額が800万円になるとそれ以上かけることができないため、保険に比べて準備できる金額が少額になってしまいます。
このように、民間の保険、共済のメリット・デメリットを考えると、
- 会社を立ち上げてまもなく⇒倒産防止共済から始める
- 資金に余裕ができたら⇒民間の保険を計画立てて始める
という順番で、自らの退職金を積み立てるのが良さそうです。