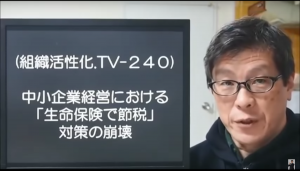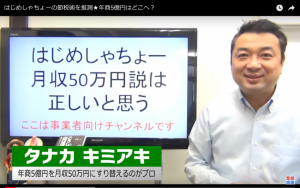企業活動が多岐にわたると裁判のリスクも大きくなります。判決が確定もしくは和解したことで、企業が損害賠償金を支払うあるいはもらうことになると、それは企業の損金・益金として計上することになります。ただし、その支払い方法(一括・分割など)の違いや、支払う側の立場によっては、判断が変わるため注意が必要です。
企業活動が多岐にわたると裁判のリスクも増える
経営危機に陥っている東芝が、米ウェスタンデジタル社に総額1200億円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こしたそうです。
少し前には、シャープがトルコ企業および中国企業から訴えを起こされたこともニュースになりました。
企業活動が多岐にわたると裁判のリスクも大きくなります。
どこの国で裁判をするかでも違いますが、日本ではまず地方裁判所から始まり、控訴して高等裁判所、さらに上告して最高裁判所までの3段階で裁判が行われます。
もちろん双方が控訴や上告しなければその段階で判決が確定しますし、確定前に和解することもあります。
いずれにしてもかなり長期間になる可能性があり、企業にとっては相当な負担となります。
裁判の勝者が手に入れる賠償金は利益としてどう振り分けられる?
判決が確定もしくは和解したことで、企業が損害賠償金を支払うあるいはもらうことになると、それは企業の損金・益金として計上することになります。
少額の場合はともかく、多額の賠償金となるとなかなか一度で支払う、受け取るということは難しくなります。
この点、法人税法基本通達では、損害賠償金の計上時期について、以下のように規定しています。
他の者から支払いを受ける損害賠償金の額は、その支払いを受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。
法人税法基本通達 2-1-43抜粋
支払う場合はともかく、受け取る場合には、まだ未収にもかかわらず全額を益金としてしまうと、手元に金銭が無いのに税金だけ支払わなければならなくなってしまうため、入金があったときに益金とすることを認めることで、企業の負担を減らそうとする趣旨の規定です。
さて、この規定には「他の者から」という条件が付いています。
これは、企業の損害賠償請求は何も会社外部に限らず、取締役や従業員など、会社内部の不正による場合もあることを指しています。
たとえば、営業担当が外注先と結託して、架空の請求書を会社に請求させたうえ自分に還流させる、経理担当者が書類を改ざんして会社口座から横領する、といったニュースもよく見かけます。
会社側は、発覚した時点で当然賠償請求することになりますが、同時に税務上のリスクも抱えることになります。
会社の揉め事は起きないに越したことはない
上記のような問題が発生した場合、会社の経理上は不正の分だけ多く経費が計上されていたことになります。
すでに述べた基本通達では、会社内部の者への適用はないため、全てさかのぼって修正しなくてはなりません。
それだけではなく、その不正をした人間が役員などの重要な役職者であったり、経理部長などお金を統括できる立場であると、“会社の行為と同一視できる”と判断されて、仮想隠蔽を伴う行為=重加算税の対象とされてしまいます。
揉め事はどんな形であっても、なるべく避けられるような仕組み作りが必要です。
Photo credit: JD Hancock via VisualHunt / CC BY