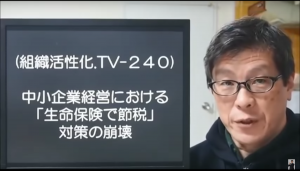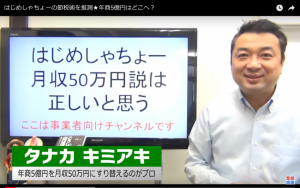アップルが1980年代に考え出した租税回避方法は、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチと呼ばれています。11月にタックスヘイブン大国であるアイルランド政府が、米国アップルへの税優遇を違法と判断されたことを受けて、EUへ訴訟を起こしており、来年以降もこの言葉に注目が集まりそうです。
来年以降もダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチはビッグキーワード
11月前半に、多国籍企業の多くが本拠地を置くアイルランド政府が、米国アップルへの税優遇を違法と判断した欧州委員会の判断を不服とし、EUの一般裁判所に正式に提訴する事態が起きました。
アイルランドには、アップルをはじめとして、グーグルやマイクロソフト、それにフェイスブックなどの国際的なテクノロジー企業や多国籍企業が拠点を置き、アイルランド政府が用意した様々な税制優遇策を活用した節税を行っています。
もともとアップルが1980年代に考え出した租税回避方法は、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチと呼ばれていますが、もしも仕組が崩れてしまえば、資源の少ないアイルランドでは企業の流出が始まり、雇用の减少や税収の低下が避けられなくなります。
この危機的な状況をなんとしても脱するため、アイルランド政府は提訴したというわけです。
裁判は長引くことが予想され、来年以降、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチは更にキーワードとして取り上げられそうです。
そこで本稿は、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチがどんな租税回避方法なのか、わかりやすく説明したいと思います。
ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチの仕組み
まず、なぜ「ダブルアイリッシュ(2つのアイルランド)」なのか?という点からご説明しましょう。
アイルランドは税金が安く、パナマやバージン諸島と同じく、いわゆるタックスヘイブンと呼ばれる国の一つです。
ただし、アイルランド1国だけで租税回避を実行すると「タックスヘイブン税制」によって、本国(アップルならアメリカ合衆国)に税金の差額を支払う必要が生じます。
そこでアップルは、同じくタックスヘイブンの国を間に挟み、その第三国を通して2つ目のアイルランド法人を作ることで、法律の適用範囲が本国に及ばぬようにしてしまうことを思いつきました。
こうすれば、本国は税金の徴収が非常に難しくなるからです。
アップルの場合、サンドイッチ(挟んだ)したのは、ダッチ(オランダ)でした。
オランダとアイルランドの間には租税に関する条約が結ばれており、アイルランドからオランダに対するロイヤルティ支払には源泉税の徴収が適用されません。
これら一連の流れにより、アップルの租税回避行為は「ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチ」と呼ばれるようになりました。
ちなみにアップルは、アイルランドの第1法人の管理会社を英国領バージン諸島に置くことで、第1法人の法人税も回避しています。
そのような意味で、アップルはダブルアイリッシュ・バージンサンドイッチも行っているわけです。
ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチの節税効果〜具体例
それでは、ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチは、どのような節税効果を生み出すのか、一つの簡単な例から考えてみましょう。
多国籍企業Aが、日本法人で100億円の税引前利益を生み出しました。
そこで、多国籍企業Aはアイルランドにある管理会社Aダッシュを利用して、FC料、ライセンス料として日本法人に100億円を請求します。
すると、どうでしょうか?
多国籍企業A・日本法人の利益はゼロになり、日本政府に本来なら30億円以上(実効税率約34%)を支払わねばならなかったところ、税金を支払わないで済みます。
しかも、アイルランドは税金が安い(12%前後)ので、日本に払うより少ない税額で済むのです。
これは「税源侵蝕」と呼ばれています。
日本では、こうした方法に対する規制や法整備のおかげで、二国間程度の租税回避なら簡単にバレてしまいます。
しかし、オランダやバージン諸島など、第3国、第4国を経由した「ダブルアイリッシュ・ダッチサンドイッチ」になってくると、これが分かりにくくなります。
さらに、タックスヘイブンにある企業は、住所、代表者不明の匿名企業にすることも出来るため、余計にお金の流れが見えにくくなるのです。
日本政府がマイナンバー制度を導入したのは、法人はもちろん本人確認を容易とすることにより、こうした租税回避行為を防ぐことが目的の一つです。
もちろん、アップルやグーグルをはじめとする、租税回避行為を積極的に行っていた企業も黙ってはいません。
彼らが電気自動車や人工知能など大きな投資が必要なビジネスに乗り出したのは、これら新分野へ乗り出して費用を計上することと無関係ではありません。
イタチごっこはこれからも続きそうです。